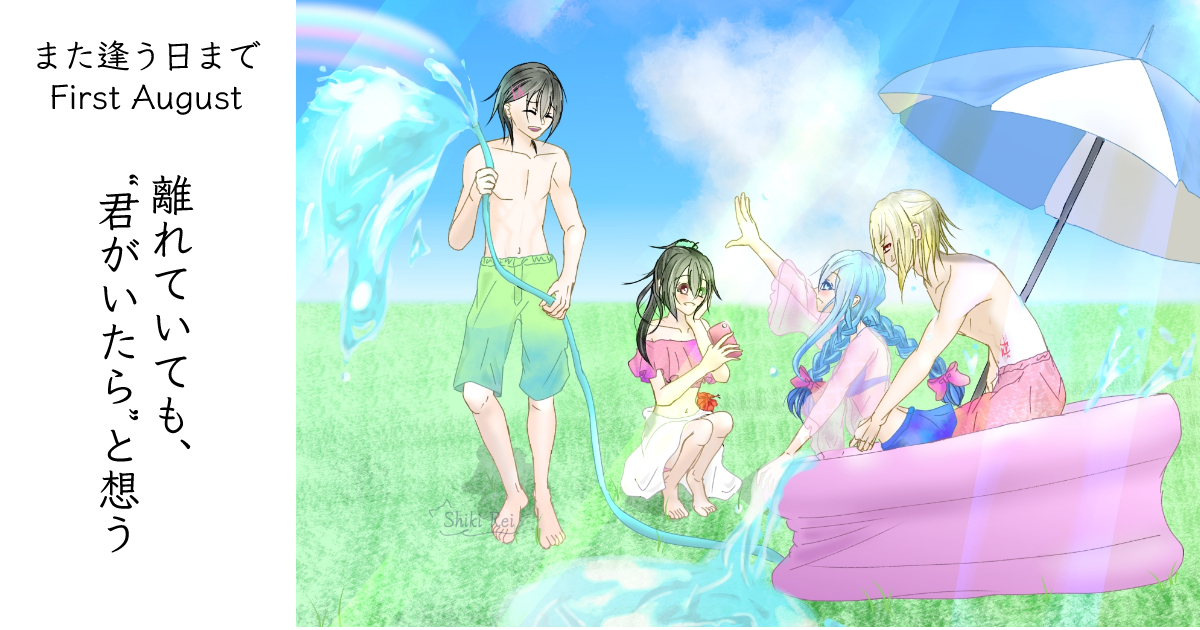「…」
「……言っていた割には元気そうじゃないか?」
「…うん」
夏まっただ中の笑守人学園。恋人様と、花壇の前で二人して首を傾げる。
カリナとレグナがフランスに行って、ちょっと。
夏だからなるべくこまめにお水上げなきゃってことで、二人がいない間はわたしとリアス様でペチュニアのお世話。ほんとは毎回一緒に行きたいんだけど、夏はとくにリアス様が外に行くのだめって言うから、いつもはお留守番。
ペチュニアが元気ないって聞いてた不安もありつつ、こんな真っ昼間に、しかも恋人様とちょっとしたデートみたいな感じで外出れるってことでわたしは朝からわくわく。ただまぁ手をつないで道を歩きましょなんてそんなかわいらしいことはかなうはずもなく。当然家の目の前からテレポート。
若干しょんぼりしながら来たペチュニアの前。デートじゃない本来の目的を思い出して、ペチュニアをしっかり見れば。
リアス様が言ったとおり、そんなに辛そうじゃない、まだ葉っぱのままのペチュニア。
「…カリナ、めちゃくちゃ申し訳なさそうだったからよほどなのかと思ってた…」
「写真もショックすぎて忘れたと言うからだいぶやばいのかと思ったよな」
うなずいて、ペチュニアをじっくり見る。
…うん、そんなに言うほどしんなりとかはしてないよ?? 大丈夫だよカリナ、どっちかっていうとちょっと生き生きしてる方だと思うよ。たぶんフランス行く前にたっぷりお水上げてたからだと思うんだけど。
とりあえず元気だよって写真送っとこうかな。
暑さにふって息を吐いて、首のあたりに流れてきた水をぐいって肩でぬぐってから、リアス様のポケットに入ってるスマホに手を伸ばしたら。
ぱしって腕を取られて止められた。
「…」
「……」
思わず見上げたら、じっとわたしを見る紅い目。
「しゃしん…」
「……」
思ったより小さく出た声に、リアス様はまだわたしを見つめたまま。え、スマホ取らせてください。あなたのじゃないと送れないんですけど。
あ、別に写真撮るのはリアス様のじゃなくてもいいんじゃない? わたしので撮ってからリアス様に送って、それをカリナに送ればいいんだ。よしそうしよう。
取られていない手を、自分のバッグに伸ばした──
「!」
のに、ぐいって引っ張られてから抱き上げられて、それも止められる。
ちょっとどういうことなの。
下になった紅い目を睨む。
「わたしは写真を、とりたい」
「そろそろ時間切れだ」
言いながら、リアス様は体を支えてない方の手でわたしのほっぺに触る。いつもなら暖かい手が、ほんの少しぬるい。
「きついだろう」
「へーき…」
「水分」
「…」
強めな言葉に、文句は言わずにバッグの水筒を出す。リアス様が日陰に移動してくれてる間に、氷でキンキンに冷えたスポーツドリンクを飲み込んだ。
少し暗くなった中で、ほっと息をついて、リアス様の肩にもたれかかる。
「…」
「図書館行くぞ」
「しゃしん…」
服を引っ張って小さく言ったら、ちょっとの沈黙。
じりじり、暑い。ほんの少しだけ、くらくらしてる気がする。それをわかってるリアス様の手が、またほっぺにふれた。
「……」
「…りあすさま」
息と一緒に出る声に、ため息を吐いて。
「……お前がいい子にしていたなら、夕方また寄ってやる」
条件みたいな、約束をこぼす。
「ほんと…?」
「いい子にしていたら、な」
「ん…」
あくまで約束じゃないなんて言うみたいに歩き出すリアス様の腕の中で揺られながら、お礼を言うようにすりよった。
ちょっとだけ暑いけれど、この暑さは、辛くない。
心地よいあったかさに、図書館に行く間だけ。目を、閉じた。
♦
「刹那」
大好きな声が聞こえる。
「ん…」
ふわふわした中で、体が揺れた。
「刹那」
「んー…」
背中がとんとんって叩かれて、ぬくもりに抱きつく。
「なぁに…」
「起きろ」
えぇ…?
起きてるんですけど。
「刹那」
「んぅ…」
起きてるのに、いつもみたいに起きろって肩を揺すられる。言わなきゃだめ?
息を吸って、紡ぐ。
「おぃてう(おきてる)…」
あれ言葉がおかしい。
わんもあたいむ。
「…おいえるー…」
おかしい。思った言葉が出てこない。そんなわたしにあきれたように笑う声が聞こえて、また背を叩かれた。
「言えていないからな。目を開けろまずは」
言われるがままに、重たいまぶたを開ける。
視線の、先には。
「あは、おはよう氷河さん」
いつもと違う、銀髪のヒトがいた。
「…りゅーじゃない…」
「炎上君こっち」
指をさされた方向を見たら、今度はちゃんと、大好きなヒト。
「おはよう」
「…寝てた…?」
「それはもうぐっすりとな。あまりに心地良さげだから歩いたわ」
「わぁおつかれさまです…」
お前のせいだろうってほっぺをうりうりしてきたのに、ほっぺをふくらませてにらむ。それに、いつもみたいにつままれて空気を抜かれた。そのままむっとしてたら、
「……ふふっ」
笑い声が聞こえて、そっちを見る。せんりが、おかしそうに笑ってた。
「…?」
「あはは、ごめん。テストの時も思ってたんだけど、二人とも、恋人って言う割には兄妹っぽいなって」
ご所望ですか。ぱっとリアス様を向いて、わざとまゆげを下げて。
「おにーちゃん…」
「やめろ結構それクるんだ」
わぁ予想以上に効果バツグン。
「兄妹プレイがおこのみですか…」
「できないくせにプレイだとか言うな」
「ぁたっ」
おでこをつつかれて、またリアス様をむっと見上げる。だけどリアス様はなんてことないみたいに、わたしを抱えて歩き出しちゃった。
そういえばここどこ?
周りを見回したら、後ろをついてくるせんりの周りに本がいっぱい。
「ここ図書館だったの…」
「朝お前が来ると言ったんだろう。夏休みに読むからと」
「うん…」
さっきと違って涼しい場所で、あったかくなったリアス様に抱きつく。うりうりしてたら、せんりと目があった。
「なぁに…」
「あ、えっと、うちの妹も昔こんな感じだったなぁって」
「妹…いそう…」
「面倒見良さそうだしな」
「そうかな」
少し照れたせんりにうなずいてから。
「そういえばせんりはなんで図書館いるの…?」
「わあ氷河さんいきなり話題変わるね」
「驚くだろう」
え、そんなことなくない?
「ちゃんと区切りはついた…」
「お前の中でだけな」
「そんなことないもん…」
「い”っ」
髪の毛ぐいって引っ張ってから、せんりにもっかい首をかしげる。
「おべんきょう…?」
「う、うんそうなんだけど……炎上君大丈夫……?」
「いつものこと…」
「こいつの力で抜けていないだけましだ」
ちょっと聞き捨てならない。
「なんで龍はわたしをか弱い女の子って認めないの」
「何故刹那は自分をか弱い女の子ではないと認めないんだろうな?」
「どこをどう見てもか弱いじゃんっ」
「あぁ見た目”だけ”は認めてやる。どこからどう見てもか弱い少女だな」
「”だけ”を強調しないで」
体を離して睨んだら、ため息。紅い目が、こっちをあきれたように見る。
「いいか刹那」
「なぁに」
「か弱い女は握力60もないんだ」
「わたしの握力は58なんですけど???」
なんで盛るの意味わかんない。ちょっとせんりがびっくりした顔してるじゃん。
「ちがうんだよせんり、わたしの握力は58なの、60もないの」
「四捨五入すれば一緒だ」
「こういった、数字は、ちゃんと、正確にっ」
「いてぇよ髪の毛引っ張るな」
「引っ張られることする龍が悪い」
「引っ張る刹那が悪い」
「刹那悪くない、被害者」
「髪の毛窃盗しようとする容疑者だろう。抜けたらどうするつもりだ」
「大事に保管する」
「華凜でもそこまで言わねぇぞ……」
なんて、話がそれかけたところで。
「ふ、ふふっ、あははははっ」
おっきな笑い声が聞こえた。
思わずそっち見たら、せんりがまた笑ってる。
「は、あははっ、はぁ、おかしっ……」
「せんり、ここ図書館…、おっきな声で笑うのはちょっと…」
「笑わせたのは氷河さんたちだよ、ふふっ」
そんな笑わせるようなことした?
リアス様を見てみるけど、首を傾げる。
「これが通常だが」
「はぁ、あは、愛原さんと波風君もすごいね、毎日こんな面白い人たちと一緒で普通だなんて」
「どちらかと言えばあいつらの方が面白おかしいことをしているが?」
「華凜はいつも楽しいこと持ってくる…」
「俺としては迷惑ばかりなんだが」
悪い気はしてないくせに、っていうのは黙っとこ。
あいかわらずリアス様に抱っこされながら奥の方に歩いて行って、窓際だけど日の当たってないとこの席に降ろされる。
「はー、おかしかった」
「楽しかったなら何よりだ」
言いながら、リアス様はわたしのほっぺに触れる。体温と、体調たしかめるみたいにわたしに視線を合わせてしゃがんだ。
「も、へーき」
「あぁ。水分は摂れよ」
「さっき飲んだ…」
「寝ていたんだからもう一回」
どこまでも過保護なリアス様にちょっとだけむくれながら、言われたとおりにまた水筒に手を伸ばす。
ちょっとだけ氷がとけて、さっきよりもぬるくなってた。
「氷河さんはもう大丈夫?」
「あぁ」
「来た時氷河さんの方が汗びっしょりでびっくりしちゃったよ」
「夏、よわいらしいの…」
「えっと、本人的には無自覚なんだね……」
「もう少し自分に目を向けてくれると助かるんだがな」
特異体質だから仕方がないって言いながら、リアス様が隣に座る。本探しに行こうかな。まだだめかな。なんてリアス様の様子見てたら、せんりが「あっ」って声出した。
「どうした」
「えーと、熱中症になりやすいんだよね?」
「……まぁ、簡単に言えばな」
「じゃあ塩飴食べる? 少しは役に立つかも」
せんりがバッグの中から出したのは、夏によく出るようになった塩飴。それを見て、反射的にリアス様を見る。
紅い瞳は、ちょっと気まずい顔。
「あ、苦手だった?」
「いや、苦手ではないんだが」
むしろ甘すぎないからまだリアス様的にはいいよね。
でもこの人が気まずい顔をしたのは、苦手とかそういう話じゃないのを、知ってる。
「……不快な思いをさせる」
どこまでも、優しい人だから。
「不快?」
「刹那にそれをと言うのなら、俺の分ももらう」
「あ、うん、それはもちろん」
「確認のために」
リアス様の言葉に、せんりはきょとんってする。誰でもわかる、このあとの言葉。
「えーと、なんの?」
それに、申し訳なさそうに目をふせてから。
「……変なものが、入っていないかどうか」
言った言葉に、せんりの目が、開く。
組まれたリアス様の腕に、そっと、手を置いた。
心配性で、過保護なリアス様。
いつだって一緒にいてくれて、起きる時はわたしより先に、寝る時はわたしより遅く。
幼なじみ以外から渡される食べ物は、リアス様が先に食べてから。
「……昔、刹那にと渡されたものに、毒が入っていたことがある」
「毒……」
「刹那自身、たまたま味を知っていた菓子だったし、口にした瞬間変な味がすると言ったから吐き出させて、大事には至らなかったが」
そのときから、もらうものはリアス様が先に食べるようになった。
「……恐怖心から抜けない癖だ。以降は俺が食べて何も無ければ刹那にもやる」
わたしが、安心して食べれるように。
これまでずっと、ずっと。
「……もしかして、パーティーで炎上君が氷河さんと同じもの食べてたりとか、体育祭でのパン食いミッションで氷河さんが炎上君のとこに行ったのも……?」
「俺が食べたあとでない限り食べるなと言いつけているからだ」
「……そっ、か」
元から静かな図書館なのに、妙にしんとしてる気がする。
なんとなく、重くて。リアス様に、寄り添った。
ねぇ、どうか。リアス様のこと、嫌な風に思わないで。誰にでも優しいリアス様。仲良くなってきた人相手に、好きでやってるわけじゃ、ないから。
考えてるせんりに、願う。
「……なんだ」
でも、せんりの口から出てきたのは、思ってたのと全然違う言葉だった。
「俺てっきり、炎上君が食いしん坊なのかと思ってた」
真剣な顔で言われて、思わずわたしもリアス様も、固まっちゃう。
なんて??
食いしん坊??
「……何故その発想に至ったんだお前は……」
びっくり発言にリアス様頭抱えちゃったよ。
「だって、こう、なんだろうな……氷河さんが食べるもの分け合ってるってイメージでね、あぁ炎上君は恋人と同じもの食べたいくらい氷河さんのこと大好きで、あとは意外と食いしん坊だったんだなぁって思ってたよ」
あとは、
「今の話聞いても炎上君が氷河さんのこと大好きなんだなってことしかよくわかんなかったかな」
なにをどう変換したらそうなるんだろう。さすがのわたしでもよくわかんない。
いまだに驚いて固まってるわたしたちに、せんりは「だってそうでしょ?」って続ける。
「昔毒が入ってたってなったら誰だって警戒するし……。別にやろうと思えばもう食べるな! なんてこともできるはずなのに、炎上君は自分で毒味してまで氷河さんの食べたいものを食べさせてあげてる。俺からしたら大好きなんだな、そんなに大切なんだなってしか思わない、かな?」
「お前あの情報でよくもまぁそこまで考えられるな」
「せんり、すごい…」
「あは、なんか二人の感じが物語に出てくるキャラクターみたいで。よくあるじゃない、王様のを先に毒味して食べる、みたいな。そんな感じなのかなーって」
せんりの笑った顔に、すごい不思議な人って思いつつも、ほっとしたような気分になる。
とりあえず、
「……せんり」
「ん?」
リアス様の腕に、ぎゅってして。
「りゅーのこと、嫌な風に思わないでくれて、ありがと…」
驚いた顔のせんりは、またすぐに笑った。
「どういたしまして。でもきっと、美織ちゃんやユーア君たちだって同じこと言うと思うよ」
「……入学している俺達が言うのもなんだが、笑守人の奴らは不思議な奴らばかりだな……。過保護も含め、普通なら嫌な顔をして去るようなものだろうに」
「多分炎上君の過保護は地味に面白いものって見られてると思うよ」
リアス様、何故だって顔してるけどたぶん行き過ぎで逆にどこまでやるんだろうってみんな思うんだよ。
わたしも自分にやられてなかったら思うよ。
「でもまぁ、とりあえず嫌われてるとかそんなのがなくて俺的にはよかったかな、なんて」
「そもそも嫌いなら近づきさえしない」
「あは、だよね。――じゃあ、はい」
笑いながら、せんりが手を差し出す。リアス様が伸ばした手の上に乗ったのは、二つの塩あめ。
「炎上君の分もあるならいいんだよね」
「……助かる」
ほっとしたように言って、リアス様は先にあめを食べ始めた。あ、もしかして結構甘いやつ? 顔ひきつった。
「あ、ねぇ?」
口元押さえはじめたリアス様を見つめてたら、せんりの声が聞こえてそっちを向く。今度は、不思議そうな顔。
「純粋な疑問なんだけど、いいかな?」
「……なんだ」
わぁリアス様すっごい死にそうな顔。
「先に炎上君がそうやって食べてるわけだよね」
「あぁ」
ガリって噛む音が聞こえてから、袋を開ける音がした。食べていいんだって、リアス様に向く。
「例えばの話、もしも両方に毒が入ってるとしたら?」
リアス様があーんってしてきたあめを、ほうばる。ちょっとしょっぱくて、でもあまい。そっちのおいしさで、せんりの声はあんまり聞こえてなくて。
「……」
「両方死んじゃうかもしれないっていうのは、大丈夫なの?」
いつもみたいにおいし、って伝えるために上を向いたら。
「……」
紅い瞳がわたしを見てた。
じっと、愛おしそうな、でもどこか、おかしい愛がこもった目。
「……もしも、俺達の飴両方に毒が入っていたら、な」
話半分で聞いてたせんりの言葉を、わたしにも聞かせるみたいに言う。
歪んだ目から離せないでいたら、するってほっぺにあったかい手が伸びてきて。
「このまま、毒に侵されて両方死ぬとしたらどう思う」
なんて、言った。
「…」
答えを聞かなくてもわかるでしょう?
その答えも、わたしの思いも。わかってるリアス様は、あやしく微笑む。わたし今、どんな目をしているんだろう。
あなたが満足そうだから、きっと同じ目をしてるのかな。
いつもみたいに近づいてきて、おでこを合わせる。
けれどあなたの視線は、一度横へ。
「閃吏」
他人を呼んでるはずなのに、甘い声が心地よくて。きれいな顔から、目が離せない。
「もしこのまま、両方死ぬとするのなら」
紅い、きれいな目がこっちを向く。
愛しげにほほえんだあなたの口から、言葉がこぼれた。
「それは本望だ」
甘い、甘い。けれどどこか、狂気を含んだような声で。
でも、逃げようなんて、思いもしなくて。
「なぁ、刹那?」
その声に、勝手にうなずいてしまう。満足そうなリアス様は、ほっぺに置いてた手を首に回して、わたしを抱きしめた。
肩に頭を乗せて、横を見たら。
おどろいてて、少し顔が赤い、せんり。
おどろいてることも、顔が赤いのも、なんでかはわからなくて。
でもすぐにどうでもいいやって思って、リアス様にすりよる。
あったかい。また眠くなりそう。
その中で聞こえたのは、二人の声。
「え、炎上君たちってやっぱりこう、物語のキャラクターたちみたい、だね。主人公とかみたいな」」
「あんなきれいで純粋な奴らじゃない。どちらかと言うとあれだ、選択肢ゲームでよくあるヤンデレルートの人間」
優しいリアス様の声に、また眠くなりそうだけど。するって体が離れてく。
反射的に、追いかけてお腹にぎゅってした。
「刹那」
「もうちょっと…」
「甘えられるのは大変嬉しいが外なんだここは」
「さっきまでぎゅってしてた人が何言ってんの…?」
「あはは、確かに炎上君の方が周り的にはやばかったよね」
図星なのか、ぐって黙るリアス様。息をついて、わたしを見る。
「だめ…?」
「……俺はなるべく早く帰りたい。体調が落ち着いたなら本を選んで帰るぞ」
「五分だけ、ギュッて…」
なにかに耐えるみたいなリアス様。ほんとに、ちょっとだけ。
ね? って首を傾げたら、深いため息が出てきた。
「……いい子にしていたらの条件を忘れたか」
いい子にしていたら。
言われて、首を振る。
リアス様との約束、忘れるわけない。
「いい子にしてたら帰りにアイス買ってくれる」
「悪いが初耳だ」
「ふはっ」
あ、またせんり吹き出した。
ぎゅって抱きつきながら、せんりを見る。
「せんり大変だね…今日腹筋大丈夫…?」
「ふ、ふふっ、どっちかっていうと氷河さんのせいでこうなってる……、ふはっ」
「おかしい…」
「俺としては自覚のないお前がおかしい」
そんなことないもんってほっぺ膨らませながらリアス様の方に向くけど、空気を抜かれるだけ。
「はー、おっかしー……。たまに恋人らしいけど、やっぱりどっちかっていうと兄妹だね二人は」
「おにーちゃんアイス…」
「やめろ」
あまりにもクるのかリアス様頭をかかえていらっしゃいます。
「お前本当に帰りの花壇無しにするぞ」
「やさしー龍はそんなことしないもん…」
「アイスか花壇かどちらかにしろ」
なにそれずるい。
「刹那いい子にしてたもん」
「たぶらかそうとする奴のどこがいい子だ」
「たぶらかされる龍が悪いの」
「龍は今回被害者だろう」
「わたし毎回容疑者」
「実際容疑者だろうが……」
なんて攻防をしはじめたら、くすくす笑い声が聞こえて。
「あの」
声をかけられて、二人でそっちを見る。楽しそうなせんりは、笑いが収まってから。
「エシュト学園、夏休みでも購買空いてるんだ。だからアイスも花壇も両方行けると思うよ」
「! ほんと…!」
「あまり甘やかさないでくれ」
「普段恋人に甘い炎上君に言われても……」
困ったように言ってから、せんりがわたしを見る。
「えっと、いい子にするご褒美がどっちかだけなら、俺が楽しませてくれたお礼にアイスの方あげるよ」
「…!」
「閃吏、さすがに」
「いいのいいの、本持ち帰るのが面倒でこっち来てるんだけど、やっぱり基本はずっと一人で暇だったし。だから良ければ、楽しませついでに一緒に購買行こう?」
なんて言われたら、わたしはもちろんうなずく。
そして、リアス様を見上げた。
合った瞳は、確認するみたいにわたしを見てた。
そしてすぐに、あきらめたように息をつく。
「……アイス食って花壇の写真撮ったらすぐに帰るからな」
「うんっ」
二人きりだとあんまりないお許しに、うれしくなって。
思いっきり抱きついた。
リアス様はそのままわたしを抱き上げて。
「たぶん人は少ないと思うんだ」
「それは助かる」
立ち上がったせんりと一緒に、購買に向かった。
その間、またあったかくて寝てたと知ったのは購買についてから。
『あたたかなぬくもりの中で見た夢は、アイスを食べながら手を繋いで花壇を歩く光景でした』/クリスティア
私の兄はよくモテる。
「レグナ様、こちらのお菓子なんていかがでしょう!」
「うん、もらっとくね」
うちには大層おモテになる王子がいるのであんまりそう見えないかもしれないんですけれども。
「こちらだっておいしいんですよ! ほら、召し上がって」
「後で食べるから、包みのままでもらうよ」
お兄さまだって、女の子が集まって動けないことは、案外ざらだったりします。
そんな目の前の兄を見て、一人。グラスを揺らした。
日本から汽車に乗って行くことしばらく。
着いた先は、半年も経っていないのに少々久しく思えるフランス。
ひとまずレグナと私は戻る家が違うので一旦解散し私はシフォン家へ。
恭しく迎えられ、まぁこれはこれはお高そうなドレスに着替えさせられ御髪も整えられながら、日本はどうですかだとかのお義父様付きのメイドの質問に適当に答え。
ばたばたと家族と会食だとか、本家扱いになるレグナのいるグレン家へ改めてご挨拶だとか、日本にいる親友と幼なじみを思い出す暇もなく数日が過ぎまして。
明日帰るというフランス帰省最後の日。
当然ゆっくりすることもなく、我々双子はパーティーにいます。
テストの会場よりも数倍大きな会場に、お偉い方やらそのご令嬢ご子息やらが集まり関係を持つために愛想笑いを浮かべて話をしている姿ばかり。
いつの時代もこういうのは変わりませんねと思いながら、もう一人。
愛想笑いを浮かべている人を見る。
「レグナ様、お飲物はいかがです?」
「大丈夫」
「ねぇレグナ様、わたくしこの前ね──」
「ん?」
その人、愛しい兄は、周りと同じように愛想笑いを浮かべて、群がる女性陣に対応していらっしゃいます。
まぁきれいな笑みだこと。本当に外面いいですよねあなた。
そんな兄に、我先にとお菓子を持ってきたり、我々双子がいない間のことを話す女性陣。一人話せば負けじと違う人が話し、それにまた──。
おそらく外付けの笑みには全く気づいていないんでしょう。何故かって? ハートが見えるんですよハートが。女性陣みんなあの、めろめろーみたいな声出してすごいんですよ、ザ・女みたいな。いや女性なんですけれどもね?
しかもそれが一人や二人じゃなく十数人。
明らかに、周りのような関係を持っておきたいみたいな感じじゃない装いで。あぁ、関係は持っておきたいですよね。あの愛がつきそうな方の関係を。
すごいですよね、何がすごいって。
これであの人自分はモテることなんてないとかあの口から発射するんですよ??
意味わかりませんよね、あのハート見えてないのかしら。外面の仮面つけるときに目も覆っているのかしら。
私たちに寄ってくる人たちのことはすぐ気づくのに。特に男。
そこまで思い至った瞬間に一瞬だけもしやそっちに──なんて思ったけれど、その寄ってきた男をすぐさま亡き者にしてしまおうとするからそれは違うなと心の中で首を振り。
「……」
手持ちぶさたにグラスを揺らしながら、兄を眺め続ける。
え、助けにですか?
行きませんよ当たり前じゃないですか。
だって女の子怖いんだもの。
もちろんありますよ助けに行ったこと。どんだけ外面が良くても内心ではめんどくさいとか思ってたりいらいらとかしてるの知っていますし。
だから行ったんですよむかーしむかしに一度だけ。
そしたらまぁなんということでしょう。
助けに行った直後は目が怖いわ心なしか舌打ちは聞こえるわ、兄を呼んだら兄妹なのに「様つけないの?」みたいな奇怪な目で見られるわ。
もう二度と女子の恋愛毎には関わるまいとそのときだけでも思いましたよ。
ただまぁそこだけで済んだらよかったんです。
問題はその次。
当時、女の子たちはパーティーのときだけでなく日常生活でもいろいろちょっかいかけてきたんですね。今で言ういじめみたいなものですね。
あ、もちろん問題はここじゃないんです。
テストのときのパーティーありましたよね。
見知らぬ人間が私に手を出そうものなら兄だけでなく幼なじみまでもがめちゃくちゃ殺すような目をしていましたね。
そこなんですよ。
実際ほんとに手を出しかけたんですようちのお兄さま。あれはほんとに怖かったあの女の子たちなんて比じゃないくらいめちゃくちゃ怖かった。
とまぁ。
ある意味一種のトラウマとなったそれと、本人からも助けなくていいとお声があったので、こうして一人脳内会話という寂しいことをしながら時間をつぶしているんですけれども。
あなたがいないと暇じゃないですか。
ずっと引っ張りだこ状態なんだから一回くらい戻ってきなさいな。ねぇお兄さま気づいてるでしょ。
そう、念を送るように見ていれば。
「!」
さすが双子と言うべきなんでしょうか。本日は髪を片方耳に掛けているというちょっと珍しい髪型のレグナがこちらを向き。
ふっと微笑んで、女の子たちに一言何か言って、私の方へ歩いてきました。
我が兄ながらその微笑みにドキッとしてしまったのは見過ごすことにしましょう。
「一人で何そんな考えてんの」
「あら、私そんなに考えてる風にしてました?」
歩み寄ってきた兄は自然に私の手からグラスを取り、中に入っているグレープジュースを飲み干していく。飲み終わったそれはそのまま、今度は頷く兄の手で揺れた。
「ずっと百面相してたじゃん」
「嘘でしょう? 私ずっと微笑みを携えていましたわ」
「俺からしたらすげぇ変わってたよ」
なんて笑って、隣に立ち、壁にもたれる。
周りを見回す兄を見ながら、茶化すように聞いてみた。
「もういいんですの?」
「ん?」
「女の子たち。ずいぶんおモテになっていたじゃないですか」
「まさか。ただの機嫌取りだろ」
この人やっぱり目も覆うタイプの仮面付けてるのかもしれない。
しかし私の絶句など目に入らないのか、あたりを警戒するような目で見ている兄は肩を竦めて笑った。
「カリナがこっち見ててくれて助かったよ。おかげで逃げられた」
「……本当に自覚がないんですのね」
「こういう場で寄ってくるってなれば家柄目当てってことくらいわかるだろ」
あくまでも認めようとしない兄に、私もあたりを見回して。
ふっと、目が合って顔を少々赤らめた青年を、兄に目で指す。
「彼は?」
「ん?」
「あそこの私を見ている彼」
「あれはカリナ目当て」
どうして。
「あと向こうにいる奴もそう。他は──まだこっちの方には来てないけど、前にちょっかい出してきてたのが何人か来てるよね」
どうしましょう我が兄ながらちょっと怖い。
けれど兄はいつものようににっこりと笑うだけ。
「ほんとならこういうときリアスとクリスティアいてくれるとありがたいんだけどな」
「腹筋崩壊の引き替えに守ってもらおうと?」
「正解」
「まぁあの男無駄に顔がいいので男除けにはなりますけれども」
それを言うなら。
「あなただって顔はいいんですから、男除けになるでしょう?」
「ごめんカリナさん、地味に言い方引っかかる。顔はってなに」
「その言葉の通りですが」
「俺は中身の方がいいだろ」
今自分でわかるくらい「どこが??」って顔している気がしますわ。
「妹に手を出す輩は性別年齢関わらず討ち取りに行こうとする人のどこが良いんですか」
「カリナだってクリスに手を出そうとする奴はあの手この手使って社会的に討ち取るじゃん」
「別にクリスティアのときだけじゃありませんよ、あなたのときだってやります」
「ごめん今そこじゃない。あとリアスのときもしてやって」
「あの男は自衛が完璧すぎるから大丈夫ですよ。今も生きているんですから保証します」
その言い方だとなんかしたのって目が痛いですね。ちょっとしたお遊び程度のほら、ね? そんな感じのほら、いたずらはしましたよ、昔にね?
こっぴどく怒られて二度とするかと思いましたけれども。
今はそうでなく。
「もう少しその手癖どうにかしたらいかがです?」
「テストのとき同様、お前に害がないなら俺の手癖は問題ないけど?」
人様の命が私の手に掛かっている。
ちょっと手持ちぶさただからって髪の毛触らないでくださる? あなたのそれ恋人みたいに見えるんですよ。顔そっくりでもいろいろ疑われちゃうんですからやめてくださる?
あぁほら、我々と肉体年齢近い男女が「え?」みたいな顔してるじゃないですか。
「レグナ、おててを離してくださいな」
「別にいいじゃん、牽制にもなるし」
「あなた私の恋人ですか???」
ドッペルゲンガー並みにそっくりな人が恋に落ちたみたいな設定になるじゃないですか。
いやまぁこの場をしのげるなら別にいいですけれども。
「……」
ふと。
どこぞのうちの王子のように、髪を指にくるくる巻き付けながら私の隣に立つ心配性な兄を見て。
中々ないだろうというのは一旦置いておいて、いつの日か。
私のことを好きだと言ってくださる人が現れたら。
「……♪」
きっとその人はとんでもなく大変なんだろうなと。
上機嫌な兄を見て、思わずため息をつきました。
『きっと世界の平和は私に掛かっている』/カリナ