余裕な笑みを浮かべて私に伸ばしてくる手を、なんとか笑みを保ちながらかわす。
「あの龍が土日に外に出ようというのは意外でしたね」
「そ、うですわねっ」
せめて胴着に手をかけられまいと引いていき、隙を見て私も目の前のポニーテールの方に手を伸ばす。けれど私の方は軽々避けられ、逆に間合いを詰められた。
「っ」
「平日が刹那の療法で、土日祝日が龍、といった感じかな」
「は、いなっ!」
「おっと」
一歩後ろに引いて間合いを取り、なんとか先手を打たれまいと技をかけるため再び先輩に手を伸ばす。
「じゃあしばらくは、土日祝日は君たち双子もずっと予定ありという感じですね」
「ぉ、そらくはっ?」
かわされ、伸ばされた手から避けるのに必死でだんだんと返す言葉は曖昧に。
やはりさすがというべきか、武道となれば手も足も出ませんわ。
しかも、
「それだと君をデートに誘えないのが残念だね」
こんな余裕なお言葉まで発していらっしゃる。ギリギリで回っている頭でなんとか理解をして。
「元々っ、お受けする気も、ありませんっ、からっ!」
彼を投げるために、少しはだけている胴着に手をかける。やっと届きましたわやっとっ! あとは投げるだけっ——。
そう体勢を整えて、足に力を入れようとすれば。
「それは残念」
なんて笑って。
「っ!」
捻りかけた体は胸元をぐいっと引き寄せられて戻り。私の体は軽々と浮いて。
直後には。
「ったぁ!!」
ダァン、では済まされないくらいの大きな音を立てながら、背中には激痛。それに身悶えていれば影が差し、お相手を睨みあげた。
けれど睨みあげた先にいる武煉先輩はただただ楽しそうに笑っているだけでさらに悔しさが増す。
「俺の勝ちですね華凜。楽しかったですよ」
「〜〜〜っ、次回リベンジですわっ!」
「楽しみに待っているよ」
その悔しさを隠しもせずそう言って。
ひとまず交代だからと武煉先輩に手をひかれ、道場の隅へと移動しました。
「華凜ちゃん派手に行ったわねー」
「明日絶対あざできてそうですわ……」
「その前に君なら治せるでしょう」
「そうですけども……気持ちのあざができそうです」
「それでも果敢に挑んでく華凜ちゃん大好きよ!」
「ありがとうございます……」
武煉先輩や陽真先輩、そして美織さんと閃吏くんと被っている柔道の時間。
二年ともなれば種族も性別も問わず対戦相手を組めるので、本日は武煉先輩にお願いしたんですけれども。
「予想以上にお強いですしめちゃくちゃ痛いですね……」
「これでも手加減はしているんだけれどね」
「本気出したら武闘会のときみたいに折っちゃうのかしら」
「まぁ相手の体重とかにもよるけれど。本気のときは陽真なんかしょっちゅう背骨にヒビ入れたりはするかな」
普段だったなら手加減はシャクに触りますが今だけは手加減されていて本当に良かった気がしますわ。想像した未来にぞっとして、入れ替わりで入っていった閃吏くんと陽真先輩の試合を見て。
「これ閃吏くん大丈夫です?」
「投げられて動けないーなんてならないわよね」
「さすがに大丈夫だよ。元々陽真はそこまで武道は強くないしね」
「おーい聞き捨てならねぇぞ相棒ー」
「おや聞こえていたかな」
これは後ほど大乱闘な予感。
またあの体育館のような骨の折りあいかしらと再びぞっとして。
「武煉先輩」
「ん?」
「髪を触る癖をどうにかしていただきたいんですけれども」
動くからとポニーテールにしている我が髪が引っ張られる感覚に、試合からは目を背けずに呆れた声でお隣の先輩をおとがめ。けれど意に介さず、彼は私の髪をいじり続ける。
「この時間はお揃いですから。嬉しくてね」
「今すぐにほどきますわ」
「えぇ! かわいいのに華凜ちゃん!」
「ありがとうございます美織さん。あとで存分にお見せしますので」
ちょうど投げられた時に乱れもしましたし。緩く引っ張られている髪に構わず、上で髪を留めているシュシュへと手をかけました。
「本当に解くのかい? 残念だな」
「あなたが触らなければもう少し遅かったでしょうよ」
言いながらぐっと髪留めを引っ張り、髪を下ろす。まとわりついて来ようとする毛束は顔を軽く左右に振って阻止をして。
さてあとでしっかり直すとしてとりあえず結びますかと髪をまとめ始めれば。
また髪の毛を触られる気配が。
けれど引っ張られる方向が違うので美織さんだとわかりました。
「あらあら今度は美織さんです?」
「ちょっとたまにはアレンジをと思って!」
「まぁ」
優しく引っ張られる髪に、まぁいいかと諦めて身を委ねました。その光景に不満そうな声を出すのはお隣の先輩。
「俺のときと態度が違くないかい華凜」
「私女の子には優しいんですよ」
「それは知っているけれど。俺にも優しくしてほしいな」
「陽真先輩がいるでしょうに」
「相変わらずそこでくっつけたがるね」
「あいにく今はそういう意味で言ったんじゃありませんわ」
なんでもかんでもそっちに持って行こうとして。私の普段の行い故というのはちょっと気づかないフリをしましょうか。
編み込みでもしているんでしょう、左側に心地よい引っ張りを感じながら、楽しんでいるご様子の陽真先輩といっぱいいっぱいの閃吏くんを見守り。話しかけてくる武煉先輩に応じます。
「そういえば華凜、さっきの話だけれど」
「どこのお話でしょう」
「君がかわいらしく投げられたところかな」
「あれをかわいらしくというならば眼科に行った方がよろしいのではなくて? いい場所ご紹介しますよ」
「生憎俺は視力は2.0だけれど。華凜が付き添いなら行こうかな」
「私がするのはご紹介までです」
「二人とも本題に入るまでの掛け合いすごいわね」
若干笑いそうになっている美織さんには「いつもこんな感じですよ」と笑って返し、武煉先輩へ。
「それで? お話に続きはありました?」
「あぁ、デートに誘えないのが残念だねと」
私の中でそのお話終わってたんですけど。あなたの中では続いてらしたの。
「デート!? 華凜ちゃんと木乃先輩!?」
しかもこんなところでいうから美織さんがめちゃくちゃ反応しているじゃないですか。この子声大きいから閃吏くんが「えっ!?」ってこっち見たじゃないですか。違いますよ。
「デートする気は一ミリもありませんけども」
「君は相変わらず釣れないな」
「前にも言いましたが釣れたことがありまして?」
「ふふっ、ないけれどね。たまには釣れてくれてもいいじゃないか」
「もれなくお兄様も釣れてきますが」
「それでも構わないけれど。最終的にカップルさんや陽真も釣れて来そうだね」
「そうなったらあたしたちもね!」
全員集合してますね。
なにデートになるのかしら。集団デート? いやでもこの中でくっついてるのってクリスティアとリアスしかいませんし。カップルデートを見守り隊?
なんてばかなことを思っていれば、また武煉先輩からお声が。
「冗談は置いておいて。いろいろと落ち着いてきているし、俺もそろそろ君ともう少し距離を縮めたいなと思っていてね。手始めに学園外で逢おうかなと」
「あらあら、それならもう何回か逢っているじゃないですか」
修羅場やお遊びのところに遭遇した形ですが。待って美織さん、「二人ってそんな仲だったのね」みたいな期待した目で見ないでくださる?
「美織さん違いますからね。偶然逢ったんですよ」
「おやすみの日に偶然逢えるなんて運命ね!」
「その運命を華凜は頑なに認めてくれないんですよ」
これは口を閉ざすのが一番の解決策なんじゃないでしょうか。一回口閉じてみます? そうしましょうよ早く閃吏くん帰ってきてくださいな。陽真先輩も。私この空間耐えられませんわ。
ヘアゴムを通し始めた美織さんとにこにこと笑いながらこちらを見ている武煉先輩に、ひとまず口を閉ざして。
「でもそのデートが今、土日華凜ちゃんが予定入っちゃうからできないのよね」
「そうなんですよ。ちょっと困っていてね」
「あ、じゃあ放課後デートとかどうかしら! 学生らしいわ!」
「あぁ、それはいい案ですね美織。龍たちと別れたあと西地区の方に向かってもいいかもしれない」
「どうして行く方向で話が進んでいるんでしょうかね」
勝手に進んでいる話にすぐさま口を開いてしまった。
呆れた目になっている間に「できたわ!」というお言葉にはとりあえずお礼を言って。今は手鏡がないので後ほど髪型を確認させてもらうことにしまして。
「似合っているね華凜」
「ありがとうございます。お話を戻しても?」
「こんなかわいい姿の状態でデートのお誘いかい?」
「胴着のお姿でデートにというのはなかなかシュールな光景ですけども」
そうでなく。
「何度も言っている通り、デートに行く気はありません」
「えぇっどうして!?」
どうしてあなたがそんなに残念そうなの。
「その気がないのに行くのも失礼でしょうよ」
「もしかしたら行ってその気になるかもしれないじゃない!」
「いやありませんけども」
「俺はその気にさせる自信あるけどな」
「百戦錬磨の腕がなるような感じですか。というかそもそも私に来る理由がわかりません」
「それはなかっ——」
「「“なか”?」」
突然止まった言葉に美織さんと揃って武煉先輩を見れば、ちょっと焦ったように目を逸らしていました。え、何事です?
「……言えないような理由で私に近づいてきているのかしら」
「いや、そういうわけではなくてね」
「わかったわ! 言っちゃうと木乃先輩が恥ずかしくて困っちゃうのよ」
「そうなんですよ美織のいう通りで」
あ、珍しく嘘がわかるような笑いしましたね武煉先輩。
「なかなか言えない理由、と言いたくて」
絶対嘘。
けれど言葉巧みな先輩はもう少しカードがなければ簡単にはぐらかされてしまう。そのカードは後々集めるとして。
「私と交流してくださるのは構いませんが、そう言ったことは違う、あなたに寄ってくる女性にお願いしたらどうです?」
バテてきた閃吏くんが陽真先輩に詰められている光景と、時計がもう少しで授業を終えることを告げようとしているので、立ち上がる。
「別にデートもお試しじゃだめなのかしら?」
「あなた木乃先輩推してきますね……」
「木乃先輩だからってわけじゃないけれど」
「それはそれで傷つくな美織」
爽やかに笑った武煉先輩に、美織さんはお茶目な笑みで返して。
「せっかくのお誘いだもの! 行ってみてやっぱりだめならもっとしっかりお断り、それなら木乃先輩だって誘ってこないかもしれないじゃない!」
ねぇ、と聞いた美織さんに先輩はほんの少し曖昧に笑って返したけれど。彼女はそれを気にすることなく、私に向いて。
「普通に遊ぶ、というような感じで言ってみてもいいんじゃないかしら?」
首を傾げてくる美織さんには、申し訳ないけれど首を横に振りました。
「武煉先輩にお気持ちがあるかは置いておいまして。“デート”というならば中途半端な気持ちでお受けはしませんわ」
微笑んで返せば、二人ともきょとんと首を傾げてしまう。当然の反応ですよね、なんて笑って。
「それは何故か聞いても?」
こちらも当然というような返答に。
ほんの少し、昔を思い出して。
「中途半端な気持ちでお受けするなんて、真摯に愛してくれた人に顔向けできませんから」
ほんの少しでもこちらも気持ちがないと。
悪戯っぽく笑って。
「そういうわけですので。お言葉とお気持ちを変えて出直してくいただけると幸いですわ」
先ほどの言葉を理解するまで呆けている二人にはそう言って、チャイムの音と同時に地面に叩きつけられた閃吏くんと投げた張本人である陽真先輩のもとへ向かった。
『いつか出逢ったあなたに、私は笑顔でこれまでのことを話したい』/カリナ
いっしょにがんばっていこうねって決めた、リアス様との行動療法。
みんなにもいろんな案を出してもらって、リアス様の方の二人でのお出かけ練習は、お休みの日の日曜日、もしくは授業が早く終わる土曜日に。おでかけは最初、カリナとかレグナのおうちにテレポートなしで行くのを目標にしていって、何回か連続で無事に行けたら、西地区とかにもちょっとずつ行くことに。
わたしの方の行動療法は、リアス様とのおでかけ練習がない平日に。やり方は前といっしょで、苦手なとこまでキスしてもらって、苦手なとこが大丈夫になって何回かやっても拒絶がなければまた次の苦手なとこに。
二人でちゃんと話し合って決めて。
「……始めるか」
「ん…」
こっちもちゃんと話し合った結果。
週の始まりである月曜日から、二人の療法が始まります。
この「いつから始める」がめっちゃ言い合いになったけど。
リアス様は自分から始めたい、わたしも自分から始めたい。切りよく週の始めからはどうだってなってもお互いの週の始まりの感覚が違うからそこでも言い合い。わたしは月曜始まり、リアス様は日曜始まり。
じゃあいっそ月初めなら文句ないんじゃないかってなったけどそこはカリナたちに「そういうことするから進まないんですよ」って言われたので断念。
じゃんけんしても三回勝負の三回目が延々とあいこで勝負もつかないし。
それならどうするかってなったときに、最近他の子とも話せるからか声かければ外に出てくるようになったごろーが。
リアス様が始めたいと思ってる土日に雨が降ったらわたしの方で始めたらどうか、って。
雨の日のおでかけはもっと気軽に外出れるようになってからって決めてたし、今後もリアス様のお出かけ練習は雨で中止になることも多いかもしれない。とくに梅雨。
雨が降ってしまったら今はどうしても文句言えないし、運も実力のうちだねってことでそうすることに決めて。
見事に土日に雨が降りまして、五月三回目の月曜日。勝者であるわたしの行動療法から始まるんですけども。
「…不服そう」
いっしょになにかやるならまず自分から、のタイプのこのヒトはまだちょっと納得いってなさそう。
「……そこまで子供じゃない」
「まだほら、早かったんだよきっと…来週あるよ…」
「予報は金曜から雨だがな」
このヒト雨に好かれてんのかな。
「俺始まりだといつになるかわからないから仕方ないのもわかるが」
「リードしたいタイプだもんねー…」
「愛しい恋人の前ではかっこよく見せたいんだ」
「十分かっこいいのに…」
顔とか、ベッドに座るわたしに王子様みたいにひざまづいてくれてるとことか。
「十分王子様だよ…」
「いや別に王子になりたいわけではないが……」
「昔の王子衣装似合ってた…」
あ、思い出したら見たくなってきた。
「今度レグナに作ってもらおう…」
「もらわんでいい」
「わたしもお姫様やるから…」
「……」
悩んだな。
これは絶対推せる。明日カリナにこっそり言っとこう。
「……馬鹿なこと言っていないで始めるぞ」
「悩んだくせに…」
「療法すっ飛ばしてその口塞いでやろうか」
「そしたら問答無用で外に引っ張り出すね…」
なんて。
前だったら絶対できなかった冗談に笑い合って。
緊張もちょっとほぐれたってことで、リアス様がわたしの手に触れた。
わたしの指先に目を落とすリアス様に、口を閉じて。そっと自分の口にわたしの指先を近づけていく光景に、ほぐれたはずの緊張が戻ってきて、こくってのどが鳴った気がした。
スローモーションに見える光景にちょっとずつどきどきしながら、指先に力を入れる。
それを「大丈夫」って言うみたいにやさしく握ってくれるリアス様に、ほっとして。
「っ」
「……」
リアス様からのキスが、爪の先に落ちてきた。
やわらかくてあったかいのが指先に当たって、そっと離れて。
もう一回、今度はちょっと上にまた、キス。ちゅって小さな音立てながら、あったかいのが落ちて来る。
「っ…」
「……」
いろんなことを思い出してから。初めてじゃないけど、きっと初めてになる、リアス様からのキス。
あったかくて、やさしくて。前だったらそれで幸せで、ふわふわしたけれど。
「っ、ぅ」
今はちょっとだけ、こわさもある。
いろんな思いが駆け巡る。
ゆっくり唇が上がって来る。たしかめるように、ほんの少しずつ。
あったかいのが触れるたびに一瞬だけ、背中がぞわっとする。見上げて来る紅い目に、こわいのがちらつく。
手が引っ張られたりしたらどうしよう。抵抗できないまま、なんか、こわいこととか——
「クリスティア」
「っ!!」
リアス様を見てるはずなのに、だんだん違う光景になりかけたとき。少し強めに名前を呼ばれて我に返った。いつの間にか浅く息してる。
紅い目がじっと見つめてきてる。
「、っ、?」
「深呼吸」
「は、っ、はぁ」
言われるまま吐いて、吸って。リアス様の手をぎゅっと握った。落ち着かせるみたいにトン、トンって手の甲を指で叩かれて、ほんの少しずつ落ち着いて来る。
「っ、…」
「落ち着いたか」
そっと伸ばされた手はちょっとこわかったけど受け入れて、ほっぺをなでてくれるあったかい手にすりよった。
「どこまで行った…?」
「手の甲」
「ぜんぜん進めてない…」
「初回にしては上々だろう。俺は爪先で拒絶されるかと思ったが」
「んぅ…」
前みたいにぜんぜん進めなかったのに、リアス様はやさしく笑ってほっぺをなでてくれた。申し訳なさがいっぱいで、ごめんねって言うみたいにうりうりほっぺをこすりつける。
「少しずつ進めばいい」
「ん…」
「一緒にな」
「…うん」
そう言ってくれるリアス様にやっとわたしも笑って。
リアス様にぎゅってしようと手を伸ばしたら。
「抱きついてくれるのは嬉しいんだが」
「?」
いつもみたいに受け入れてくれるんじゃなくて、リアス様はちょっとだけ身を引く。自分でもわかるくらい悲しい顔をしたわたしに、リアス様は「嫌だからじゃない」って言ってから。
「先に、もう一回しても?」
「もう、一回?」
「キス」
言葉にぱちぱちまばたきして、首をかしげた。リアス様はやさしい顔で笑ったまま。
「嫌な記憶が残ったままは気分が悪いだろう?」
「? うん…?」
「生物みな“次も”と思えるようなことがあれば頑張れるものだ」
俺みたいに、って言うから、リアス様はそういうことあったのかな。それは教えてくれなかったけれど。
あそんだとき楽しいと、またあそぼうねって思えるから。きっとそれと同じなんだろうなって思って。
「なにするの…」
伸ばしてた両手の片方を、リアス様の前に差し出す。
「ものは同じだ。ただ苦手なところまでとか進もうとはしない」
そっと手をとられて、リアス様はわたしの手を口に近づけてく。
ちょっとだけさっきのでこわさもあったけど、ぎゅってリアス様の手を握ってこわさをなかったことにして。
あったかい唇を、爪先に受け入れた。
そのままの状態で、わたしにこわさがまた来る前にリアス様は口を開く。
「クリス」
「ん…」
「どういうのが心地いいと思う」
「ここち、いい?」
「どうされると気分がいい。さっきのであれば進むとこわいだとか、このままの方が落ち着くだとか」
どういうのが、自分にとって心地いいのか。
聞いてきた言葉を、頭の中でいっぱい考える。
いっぱい進まれるのはこわい。ゆっくり上がってこられるのも、ちょっとこわいのが来る。手が引っ張られるんじゃないかとか、そのまま怖いことされるんじゃないのかなとか、そういうのがこわい。
じゃあ、しあわせって思ったり、心地よく感じるのは、なんだろう。
「…ふれあえるのは、うれし」
「ん」
「ぎゅってするのが、ここちいー……」
そう言ったら、リアス様はわたしの指から口を離して。
床にひざまづいてたのから、ベッドの上に上がって来る。
「ん」
広げられた手の中に入って、リアス様の膝に乗ってから肩にもたれる。
「手に触れても?」
「ん…」
片方の手をとられて、またわたしの指先はリアス様の方に向かってった。心音を聞きながらそれを見る。
伏し目がちにわたしの指先を見つめて、そっとリアス様はわたしの指先にキスをする。ちょっとだけ肩がびくってなったけど。
「さっきより、こわくない…」
「心地いいか」
「…たぶん…?」
はじめてのことばっかりだからはっきり心地いいのはよくわからないけれど。
リアス様の音を聞いて、“リアス様がいる”っていうのは、安心する。
指先も、抱きしめられてる体も。リアス様に触れてるからか全部があったかい。
なんか、こう。
「…ねむくなる…」
「寝ても構わないが」
「んぅ…」
すぐに抱き着けるのも、ほっとする。
きっとこれが、“心地いい”?
体勢的にはこっちの方がすぐどうこうできたりするから、こわいはずなのに。
やさしく頭なでられて、ときおり指先から唇を離したリアス様がわたしにすりよって。
わたしのどこかが唇に触れること以外、いつも通りだからか。すごくすごく安心した。
「…ゆっくりでも」
「うん?」
「またゆっくりに、なっちゃうけど…こっちのが、できそう…」
「そうか」
肩に体重を預けたら、また頭を撫でてくれて。
さっきのこわいのが、安心とうれしいに変わってくれて。
これなら、また明日もがんばりたいなって思えたから。
「…♪」
ありがとうと大好きを伝えるように、リアス様にぎゅって抱きついて。
心地よい眠気に目をそっと閉じた。
『行動療法再開』/クリスティア
クリスティアと共に始まるはずだったそれぞれの行動療法。
恋人は恋愛スキンシップの克服を、俺は出掛けることを始めとした過保護の緩和を。
多少ひと悶着はあったものの、ひとまずクリスティアの方から「療法を始める」という第一歩は踏み出せたものの。
『炎上は雨男ですっ』
「蓮達と出掛けるとなるとそういうわけではないんだがな……」
俺の方は毎回雨に見舞われ、未だクリスティアと出掛けられずにいる。
五月最後の火曜、料理の時間。報告しながら込みあがってくる若干の悔しさにクッキーの生地を強めに押し付けた。
「月一回はデートしようねって目標あったんだけどね…」
「し、神的なものですかね……。行くなみたいな……」
『炎上の”行きたくない”という心情的なものでなくですかっ』
「ユーアお前自分のクッキーがあると思うなよ」
誰がうまいことを言えと。
口をつぐんだユーアにはいい子だと言って、まとまったクッキーをラップに包む。
「安心してユーア…そう言いながらちゃんとクッキーくれるから…」
『知ってるです、炎上は優しい男です』
「ゃ、優しいから刹那ちゃんがケガしないように、そ、外雨にするんですよね!」
「やめろ雫来、お前の優しさに心が痛い」
そもそも恋人に優しけりゃ出掛けるために外晴れさせるだろうよ。
から笑いをこぼして。
「冷蔵庫に置いてくる」
「は、はい! お願いしますっ!」
「♪」
休ませるためにと、ラップに包んだ生地を持って調理室の冷蔵庫へ。菓子ということでご機嫌な恋人が服の裾を引っ張りついてきているのを感じながら、頭の中では療法をどうするかということばかり。
クリスティアの方は本人にとって心地いいと思うようなやり方に変えたからか、抵抗や多少の嫌そうな顔はあるものの初日のような過呼吸は今のところなし。こちらはこのままで行けば時間は掛かっても順調に行くだろう。
問題は俺だ。
学校ならば仕方ないと出れる雨でも出掛けるとなっては少々抵抗がある。滑るわ濡れるわでできればあまり行きたくはない。慣れてくればもちろんそれもデートの醍醐味とやらで楽しめるんだろうが一発目でそれはさすがにチャレンジャーすぎる。
「しかもこれから梅雨と来たか……」
「夏から、はじめる…? 療法…」
「エイリィの結婚式がなければそれでもいいんだがな……」
「エイリィの結婚式からスタート…」
「第一回目で日本からフランスの横断か。なかなかだな」
荒療治にもほどがあるだろ。
俺の今までを振り返ると荒療治で緩和していっている傾向があるけども。
「さすがにこう……ワンクッションを挟みたい」
「てるてる坊主いっぱい作ろうね…」
「祈童の祈りつきでな」
晴れてほしい日は祈願していると言っていたから願掛けにもなるだろう。後ほど交渉させてもらうとして。
「♪」
自分の班だとわかるように名前を書いたメモをラップの上に張って、生地を冷蔵庫へ。クリスティアの身長でもよく見える場所に置いてやり、休むまではこちらも待機ということでその場を離れ。
先ほどと違って腕に絡まってきたクリスティアに内心でテンションが上がりながら、自分達のテーブルへと歩いていく。
「みんなの似顔絵てるてる坊主つくったらかわいい…」
「あぁ――」
いや全員となったらホラーじゃないか? 夜中に起きたら絶対驚くやつだろうそれ。雷とか鳴ってみろ。絶対お前飛び上がるだろ。
「……毎週一人か二人ならいいと思うが?」
「梅雨の時期ローテーショーン…」
「そうしろ」
主にお前とリヒテルタの心臓保護のために。
クリスティアに言うと絶対「へいきだもん」とか言って強行しだすのでそれは心に秘めておいて。
クリスティアを連れて雫来達がいる場所へ歩みを進めていれば。
「…!」
突然絡まっていた腕が引っ張られ、足の方向が帰る場所と変わる。
「何だいきなり」
「きらきらっ」
「きらきら?」
『どうしたですかっ』
「ぉ、落とし物ですか?」
いきなり方向転換をした俺達を不思議に思ったのか、雫来とユーアもこちらに合流。雫来の問いには首を横に振り、クリスティアが引っ張る方向へと四人歩いていく。
「♪」
ぐいぐいと引っ張られるまま進んだその先には。
「ゎ、わぁっ……!」
『きらきらですっ!』
テーブルにきれいに並べられている、クリスティアとユーア曰く”きらきら”とした菓子の数々。料理の時間にこんなのが作れるのかと思うくらいハイレベルな菓子達に、思わず作り手がいる方向を見れば。
「……」
いるのは、たった一人の赤髪少年と、その首に巻き付いている蛇だけ。無表情な少年に巻き付いているその蛇は俺達が来たことに困惑しているかのように首をきょろきょろとしていた。
「すまない突然。連れが菓子に興味を示して」
「……」
興味津々に菓子を見ている三人に代わって言ってやると、少年は無表情のまま。蛇は驚いたようにしながら同時に首を横に振る。あぁもしや蛇族か、なんてその揃ったしぐさを見て、少々表で見るのは珍しい種族に内心で感動していれば。
『ルクのお菓子、食べに来てくれたのっ!?』
少年の近くから小さな少女のような声が。
『? 声が聞こえたですっ』
「ぇっと、か、彼から、ですか……?」
「いや」
首を振ってやったのと同時に、少年―ルクとやらが耳につけていたらしい真珠のアクセサリーが光った。それを耳から取り、手のひらへと乗せれば。
『ルクのお菓子、キレイでしょうっ?』
パッと、真っ白い手のひらサイズの少女が姿を現した。嬉しそうな顔でそう言って、少女はテーブルへと降りてくる。
「精霊…!」
『イヤリングが人に変わったですっ!』
「は、初めて見ましたっ……!!」
「真珠の精霊か」
蛇族に真珠、しかも自ら媒介を変化させて人に見えるようにするタイプとはなかなか珍しい種族達に菓子からどうしても視線はそちらへと言ってしまう。少女はそれに慣れているのかにっこりと笑い、スカートの裾を持ち上げて会釈をした。
『真珠の精霊、誓真珠唯だよ。コッチのだんまりな赤髪クンは、蛇族のルク。蛇璃亜ルクと、蛇のイリス!』
紹介に合わせてルクとイリスも会釈をし。
こちらが会釈を返せば、名乗る間もなく誓真はばっと距離を詰めてきた。
『それでっ! ルクのお菓子食べに来てくれたのっ!?』
「食べていいの…?」
『モチロンよっ!!』
むしろ食べてというように誓真はひとつ菓子を取り合げる。
『きっとオイシイの! 食べて食べて!』
明るく、その輝く菓子を勧めているが。
「……」
どことなく、その目に不安が見えた。
そうして誓真が菓子を勧め始めた途端に、若干周りの空気も変わっている気がする。
探ってやれば俺達を気遣うような視線、中には憐みの視線。耳を済ませれば「大丈夫なの」という声もちらほらと。
まぁ周りがそう気にしたくなるのもわかるが。
溜息を吐いて、意識を誓真達の方へ戻せば。
「…」
「……」
『……』
いつの間にか誓真の菓子の勧めは終わっており、クリスティア達が俺を見ていた。今回ばかりは思い切り理由がわかるが、恒例ということで。
「……何故俺を見るんだろうな?」
『氷河がお菓子を食べたそうですっ』
「け、けど刹那ちゃんが食べるには、ぇ、炎上君の検閲が必要です」
そうなるよな、なんて。言外に「食え」と言われていることに苦笑いをすれば。
一つの言葉に引っかかったらしい誓真が、不安そうに俺に声を上げた。
『検閲ってなに……?』
「……」
『食べる前に調べるってコト!?』
似ているがそうでなく、と言う前に。誓真は大声で叫ぶ。
『毒なんて入ってないよ!!』
恐らく誓真が必死に菓子を勧め、しかしその勧めや見た目の良さに関わらず人が寄り付かない理由を。
『ルクは一生懸命作ってるよっ!! 変なものなんて入ってない!! アタシずっと見てるもの!! きっとおいしいのっ!!』
「しゅ、珠唯さん落ち着いて……!」
『ほんとだよっ!!』
雫来がなだめてやるも、一気に火がついてしまったらしい誓真は必死に俺に訴える。
それに、しっかりと頷いた。
「知っている」
両手を緩く上げて、敵意はないと示すようにして。
いきなり「知っている」と言われて驚き、次の言葉を言うタイミングを逃した誓真へ。
自分なりの言葉を紡いでいく。
「誤解をさせたならすまない。お前達の菓子がどうこうでなく、もともと過去にそういうトラブルがあって、刹那が食べる前に俺が一口食べるという癖がある。後々直そうと思っているものだが、今はまだそれが治っていない」
『ぇ……』
「お前達の菓子に毒があるかの検閲じゃなく、俺自身の身勝手なトラウマによる不安を解消するために一口もらっても?」
まっすぐ目を見て、言ってやれば。
『食べて、くれるの……?』
トラウマよりなにより、そのことの方が衝撃的だったようで。呆けた顔で俺に問うてきた。
それに再び頷き、ルクの方も見て。
「言った通り、俺の不安の解消のために刹那に行く前に俺が一口もらうが」
言うと、蛇の方は驚きを隠せないという表情をしながらも頷いた。それに笑ってやって。
誓真が持つ菓子へ、手を差し伸べる。
「もらっても?」
『信じてくれるの?』
最後に問われた言葉には、頷きもしなかった。
「信じるも何も、お前が言うならば真実だろう」
真実を誓い、嘘が言えない種族が言うのならば。
毒が入っていないということもすべて事実。
信じるも何もない。
そう言ってやれば、誓真は大きく目を見開く。それを横目に見ながら。
一口。きらきらと光る菓子を口にする。
瞬間調理室がざわついたが気にせず甘ったるいそれを飲み込んで。
毒がないことも、変な味がすることもないとわかっているので、今回はすぐにクリスティアの口へと菓子を持って行った。
「♪」
やっと食べれることに顔を明るくして、クリスティアは菓子を一口、小さな口へと入れて。
「おいし」
「そうか」
すぐに幸せそうに笑って、また一口と菓子を食べていく。
見届けた雫来とユーアも菓子を手にしてそれぞれ口に運んでいき。
「す、すごいです……お菓子屋さんの味っ……!」
『お店出せるですっ』
クリスティア同様、顔がぱっと綻び、菓子を堪能していく。それに誓真はだんだんと顔を明るくしていって。
『そう、そうなのっ!! おいしいでしょう!? ずっと勉強してきたからおいしいはずなのっ!!』
精霊ゆえに食べることの叶わない彼女は、おいしそうに食べるクリスティア達の周りをくるくると回る。
「もう一個いいー…?」
『モチロンっ!! ね、ルク!!』
早速食べ終えたクリスティアに、誓真がルクを見た。
見て、全員が止まった。
「……は」
赤髪のその少年が、無表情のまま涙を流している。
いや何故涙を流している。
『ちょ、ちょっとルクどうしたのっ!? なにか怖いことあった!?』
『タイミング的に炎上が泣かせたですっ』
「俺なのか!?」
「ぃ、いたいけな男の子を……! 炎上くん……!」
「いろいろと突っ込みたいところはあるが今は黙れ雫来っ」
お前が言うとカリナ同様ややこしくなるっ。
いち早くルクの元へ駆けつけたクリスティアと誓真を追い、静かに涙を流すルクへ駆け寄る。
相変わらず泣いている奴をなだめるのは苦手で、少々わたわたとしながらも。
「ど、どうした……」
クリスティアに倣って緩く背を撫でてやりながら聞けば。
「……うれし、かった……」
小さく小さく。喋ることが少ないと言われる蛇族の少年がこぼしていく。
誰も今まで食べてくれなかった菓子。
誓真が勧めてくれても、どんなに見た目をきれいにしても。毒があるかもしれないからと誰もが遠ざかったと。
ただ笑顔になってほしかっただけなのに。
おいしいと笑ってほしかっただけなのに。
そう、たどたどしく喋っていく姿が。
どことなく、大昔の自分に似ていて。
昔のように涙は流すことはないが、ぎこちなく背を撫でていた手はいつの間にか自然な動きになっていた。
そうして、口が勝手に開く。
「……いくらでも食べるが」
「……」
こちらを見上げたオッドアイをまっすぐ見つめて。
「甘いものは苦手だから基本は刹那や友人達だが。作ったものは、持ってきてくれればいくらでも食べる」
「……」
だから、
「もう大丈夫だ」
ちゃんといる、と。
いつの日か誰かに言ってやりたかった言葉を、初対面の奴に言って。
気づいたときには目の前の少年はさらに涙を流していて。
「…♪」
小さな恋人が嬉しそうに笑いながら菓子を食い始めたことに気づいたのは。
突然できた後輩の涙を止めてしばらく経った頃だった。
『自分で荒療治の方向に進んでいっているのは、未だ気づかないまま』/リアス
未来へ続く物語の記憶 May-V
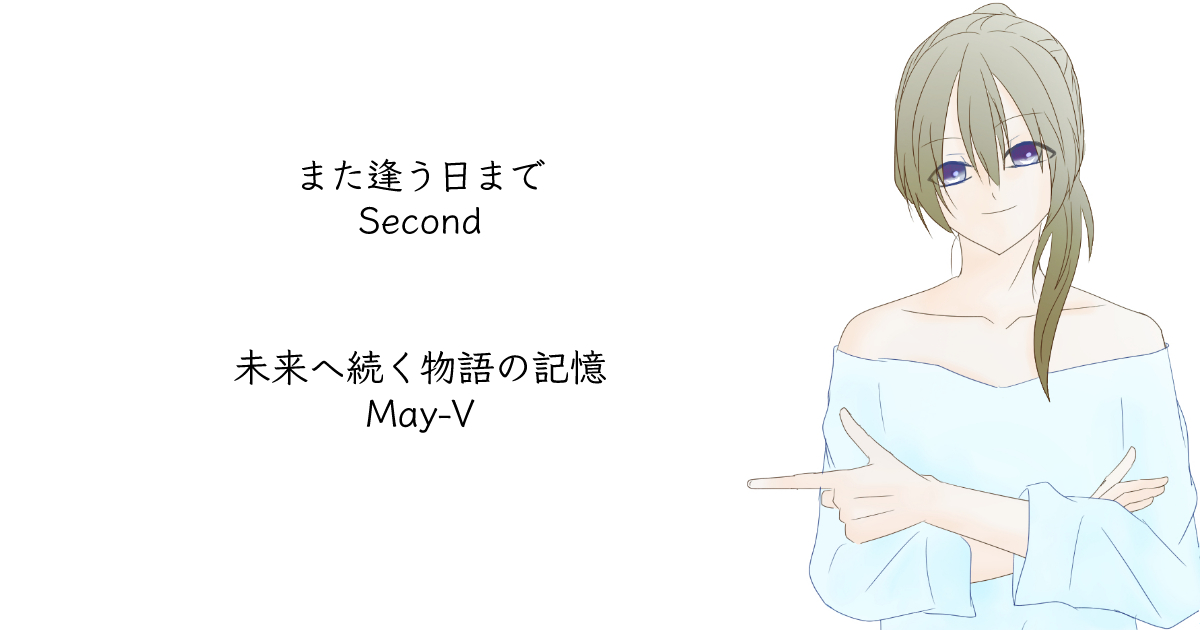 クリスティアに物語を聞かせてもらう
クリスティアに物語を聞かせてもらう