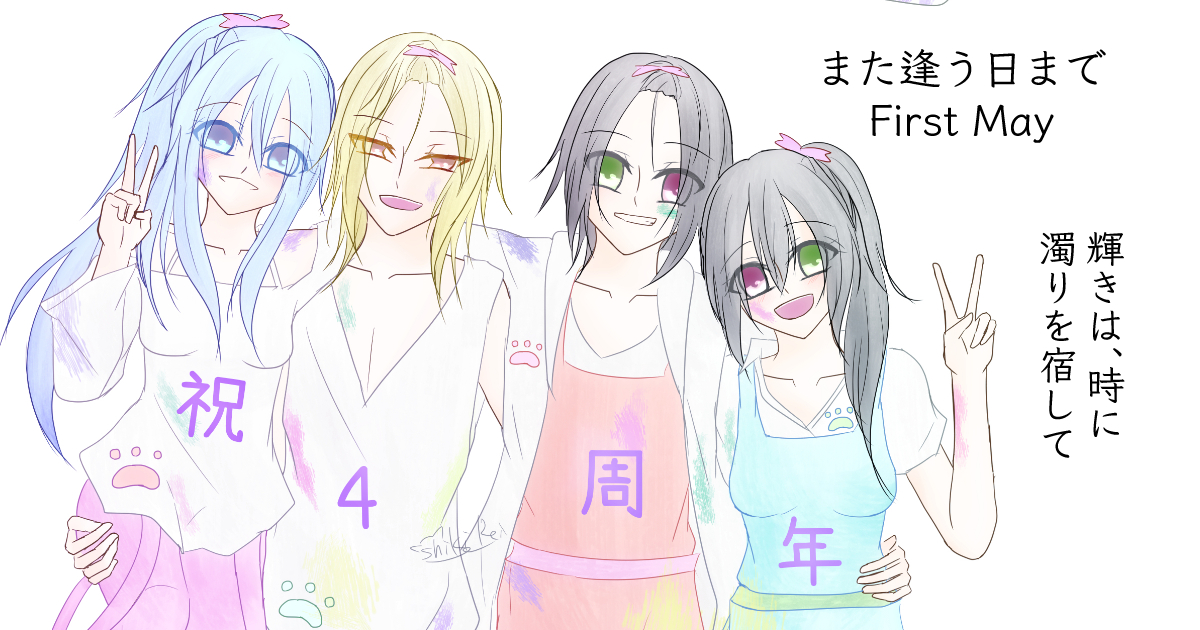ゴールデンウイーク最終日。
今日は、午前にまだ残ってる罰ゲームやって、午後にごほうびタイム。
”一日○○”とかは、半日に変更。残ってるって言っても罰消化の日にある程度終わってるから、昨日のチェスで追加になったカリナとレグナの分と、わたしの残ってる下僕カードだけ。ちなみにお相手は、ラックアップ含めて一番勝利数が多いリアス様。
九時くらいにみんなでリビングに集まって、せっかくだからお楽しみってことで残しておいた、まだ開封してない双子の罰ゲームから見てくことになり。
「もう嫌だ……」
レグナは生涯まれに見るくらいの絶望顔を見せてくれました。
「なに引いたんですか」
「ん」
顔はそのまま、レグナはわたしたちに見えるようにカードを裏返してくれた。そこに書いてるのは──
「一日チャイナ服…」
あのスリットの? 大人のお姉さまが着るとものすごくエロいあれ?
「……ほら、あなたの願望が出たんじゃないんですか」
「俺女の子に可愛い服着せんのは好きだけど、自分で女装の趣味はないかな」
「今じゃなくてこれから先あるんじゃないか」
「未来を予測した引きなの?? ねぇわ」
あまりの引きにレグナはカードを床に叩きつけてうなだれちゃった。どうしようネタ的には最高過ぎて腹筋震えるんだけど。
「カリナは何を引いたんだ」
「私ですか? これですよ」
いじけちゃったレグナは置いといて、残ってるカリナの方のカードも見る。
おっと?
「一日ナース服…」
「兄妹揃ってコスプレが趣味なのか?」
「別に好きこのんでこれを引いたわけじゃありませんよ。レグナはわかりませんが」
「俺が一番好きこのんで引いわけじゃないけど??」
「まぁ無事に決まったということで早速始めましょうか」
「カリナさん聞こうか」
「リアス、またお願いできます?」
「わかった」
「普段互いのことけなし合ってるくせになんでこういうときは息ぴったりかな」
それわたしもたまに思う。
文句は言うけど、もう諦めてるレグナは素直に立ち上がった。リアス様はカリナがどっからか持ってきたチャイナ服で魔力結晶を作って、体内に入れてから魔力を練る。
レグナに手を向けて、数秒後。体が光り出したと思ったら、魔法少女みたいにパッと一瞬で服が変わった。
赤い生地に、金色の刺繍が入ったいかにもなチャイナドレス。
わぁ黒髪にすごい似合う。
似合うんだけど。
「ズボンが邪魔…」
「チャイナ服は足が命なんですよ? 脱いで下さい」
「まじかよ」
「敗者でしょう」
なんて言われてしまったら従うしかできないので。レグナはものすごくイヤそうにズボンを脱いでいく。うわ男の子なのにすごい足きれい、ずるい。
脱ぎ終わったズボンを畳んでるレグナに、今度はリアス様が。
「スリットの位置的に下着もギリギリ見えるな」
「リアスさん余計なこと言わないで。ぎりぎりなら良いじゃん」
だめだリアス様が言っちゃったからもう気になってきた。
「下着、わたしかカリナどっちの方が着れそう…?」
「いや気持ち的には全然着れないんだけど」
「サイズ的にですよ」
「え、着る前提?」
「言っただろう、ギリギリ下着が見えると」
「だからって着るとは思わねぇよ」
ねぇ歩くとさらにその一センチが気になる。
「カリナ…」
「はいな」
見れば見るほどどーしても気になって、カリナと下着を探しに行こうと立ち上がったら。
「ストーップ」
レグナに腕を掴まれて止められてしまった。
「気になるんですレグナ」
「捲っとくから。中身まで女物にするのはちょっと勘弁して」
「おにーちゃんお願い…」
「今回だけは聞かないからね」
譲ってくれないレグナにほっぺをふくらましてみたけれど。むぎゅって掴まれて空気抜かれただけで結局履き替えてはくれませんでした。
「さて、私も着たことですしあとはクリスティアの下僕だけなんですが」
あのあと、同じコスプレお題のカリナはナース服を自分で着て戻ってきた。ピンク色のミニスカートナースでカリナが着たらエロいなって思いながらも、視線は違う場所に行く。カリナの「やっていきましょうか」って言葉にあいまいにうなずいて、隣にいるリアス様の服の裾を引っ張った。
「リアス様…」
「お前も思ったか」
あっちも同じこと思ってたらしくて、二人して双子のコスプレ──の一カ所──を見て。
「?」
「どうしました?」
不思議そうな双子たちに、かけ声もなく同時に言葉がこぼれた。
「「胸の格差が」」
「当たり前じゃね? 知ってる? 俺男の子なんだ」
「娘がつく方ですか?」
「カリナさん黙ろうか」
ほら見て、って若干筋肉がついた腕を見せてくれるけど、やっぱり目が行くのは胸。もちろん男の子なのも知ってるよ。知ってるけども。レグナって双子もあるから中性的な顔だし、女の子の服着ると似合っちゃうし。それにカリナが結構おっきめ(本人いわく普通サイズ)だからすごいごめんけど目が行っちゃう。じっと食い入るように見つめること数分。
「なぁクリスティア」
「なぁに…」
名前を呼ばれたので、隣を見上げたら。リアス様は口を開いた。
「お前とレグナ同じくらいなんじゃないか」
ちょっと聞き捨てならない。
「カリナと比べるからそう見えるだけ…わたしは控えめだけどちゃんとある…」
「レグナのサイズ測ってみたらどうだ」
「俺別に胸筋鍛えてないからふっつーにないと思うけど?」
「よければお教えしましょうか」
「その前になんで知ってるのっていうお兄ちゃんとのお話から入ろうか」
「とりあえずはっきりした数字はいらないや…」
「あらそうですか」
主張しといてあれだけど突きつけられたら悲しくなりそうだし。
「ではそろそろクリスの消化に入りましょうか? あまり長話をしていると、下僕にする時間が減りますよ」
「それはいけないな」
わたしとしてはありがたかったのに。
心の中で舌打ちをして、あごに手を添えて悩むリアス様を見つめる。
待つこと数秒。こっちを見て、口を開いた。
「罰ゲーム、とりあえずお前もコスプレするか」
この人コスプレ気に入っちゃったよ。
「えぇ…? まじですか…?」
「クリス、チャイナ服着る?」
「全力でお断りする…」
あれはスラッとしてる人が着るのがいいの。
じゃなくって。
「…やるの?」
「下僕は言うこと聞くんだろう? それにもっと可愛いお前も見たいし、たまにはいいんじゃないか」
うわぁすごいそれっぽい理由付けてきやがった。
「私もかわいいクリスティア、ぜひ見たいです」
「なんならアレンジでも加えようか?」
そしてこの幼なじみたちすぐノってくる。人のこと言えないけど。
とりあえず、
「アレンジはいらないけど着る…」
攻防しても意味ないっていうのは長いつきあいで知ってるので、レグナの方はお断りしつつ、了承。
上機嫌そうにほほえんだリアス様の「じゃあ行くか」っていう声にうなずいて、手を引かれるまま部屋へと向かった。
もうきわどい服でもなんでもどんとこい。
その後、気に入ったリアス様が午後になるまで着せ替えを楽しんだのはまた別の話。
♦
「ご満足いただけましたかご主人様…」
「それはもう」
延々とリアス様の手で着せ替えられて、罰消化のときに追加した「あーん」権利でリアス様の手でお昼ご飯を食べて、午後一時。
いつもの黄色いワンピースを着直してソファにもたれて聞くと、隣に座ったリアス様はとても上機嫌そうにうなずいた。
「あれで満足しなかったと言ったら逆にすごいですけれどね」
「あれだけやってさすがにそれはない。まぁ欲を言えば最後まで着せかえさせてくれたならもっと良かったんだがな」
「なんだ、最後は自分で服着たのクリス」
「もう午後になったからカードは無効ですー…」
「残念なことにこう言われて手を着けさせてもらえなくてな」
なんて全然残念そうじゃなく笑って、わたしの髪を自分の指にくるくる巻き付ける。とてもごきげんなときにする癖。そんなにコスプレ楽しかったのリアス様。
「では落ち着いたところで、すでに開封しているものも含めてご褒美カードの整理をしましょうか」
まぁリアス様が喜んでくれたならいっかなって、ちょっとだけ口角をあげて。
カリナの声に、手が髪の毛から離れていったのを確認してから床に降りて、それぞれカードを広げてった。
三日目に引いた、”リアス様と就寝権”はいつも通りなのでその日のうちに消化して、わたしの残りは、”お願い事一つ”と”リアス様に甘いもの買ってもらう券”。
リアス様も似た感じで、三日目の”わたしとお風呂”は消化済み、残ってるのは”お願い事一つと”、”好きなものを買ってもらえる券”。
カリナは夕飯とか、洋服とかのリクエスト系ばっかりで消化済み。
レグナもご飯のリクエストと、”買ってもらう券”は新しいゲームで決まってて……あれ?
「レグナ二枚だけでしたっけ?」
「確か全員三枚ずつになっていなかったか」
疑問に思ったことを、リアス様とカリナが聞いてくれる。
そう、レグナのカードが一枚足りない。不思議に思って、目の前に座ってるレグナを三人そろって見ると。
とてもきまずそうに目をそらしていらっしゃる。
「何引いたんだ」
「ご褒美カードなので変なもの入れなかったはずなんですけど」
「うん、うんそうね。内容的にはご褒美なのかもしれないんだ」
言って、レグナはポケットに入れてたらしいカードを取り出した。
「ただカリナさん」
「はいな」
床に叩きつけるようにして出した、そのカードの内容。
「一日女王様ってなに!!」
それを見て全員で吹き出したのはもうしょうがないと思う。
「どれだけ女物引くんだお前は、ふっ……」
「ふふっ、やはり将来への願望ですかっ……」
「違うわ」
「女王様ー…」
「もう文字だけ見たら罰ゲームでしかない…」
「だがこっから終わるまで命令できるんだぞ? いいじゃないか」
「性別に合った称号をいただきたい」
レグナの顔が切実すぎる。もうネタとしては最高すぎてこっちはおなか痛い。
「まぁとりあえず全員内容がわかったということで。早速行使していきましょうか」
「そうだな。嘆いていても始まらないぞ女王」
「ご命令はなんですか女王様…」
「なんなりとお申し付けくださいな、女王様」
「お前ら覚えとけよ!!」
レグナの叫びを合図に、ごほうびタイム始まり。
「さて、基本は願い事叶えちゃいますよ系と、あとそこのカップルは買い物権も引いてますよね」
おもにリアス様に向けて、カリナが聞く。わたしは甘いもので決まってるけど、リアス様は”欲しいもの”ってアバウトで。初日に引いたそれは、ひとまず保留になったやつ。
「欲しいもの決まった?」
「結構考えてはみたんだが……」
あごに手を添えてるリアス様は、言おうか言うまいか悩んでるみたい。
「とりあえず、言ってみたら…?」
「……買うもので思い浮かんだのが手錠しか出なくてだな」
自分で促したのすごい後悔した。
見てみんなの顔、「こいつ大丈夫?」って顔してるよ。
「……何故それが浮かんだのかしらリアス」
「いや、手が届かなかったときに引っ張ればいいなと」
あぁ、すごい実用性はあるかもしれない。
いやちょっと待って?
「リアス様、そのとき用にわたしに呪術かけてるじゃん…」
体の半分を占めるくらいある、リアス様直々に刻まれた呪術の模様に指をさす。
「昔勝手にどっか行ってけがしないようにって始めたやつでしょ?」
「そう…」
「昨日のお風呂でも見ましたが、また今回は増えてますねぇ」
「今どこ?」
「白のクロス模様が両腕両脚、紅い模様が胸中、首の裏にあるな」
「こんなにつけて手錠までいる…?」
「四月のようにテンパって呪術が間に合わなかったとき用に」
あなたどうしてわたしに呪術かけてるの。
「間に合わなかったとかで辛くなるならもういっそのこと完全監禁しちゃえばいいじゃん」
「なにそのヤンデレルート…」
待ってリアス様その手があったかなんて顔しないで。やりかねない。
「カリナ、リアス様が行き過ぎてナイフとか持ち出したらテレポートしてっていい…?」
「うーん、お迎えしたいのは山々なんですが、一緒に飛んできそうなのでお断りしますわ」
「もしくは先回りしてそうだね」
「そもそも逃げ出すなんて選択肢を与えるわけないだろう」
あ、ですよね。たぶん今がそれの答えになってる気がする。
「まぁさすがに手錠にすると変態かと思われるからなしにしてだな」
「すでに変態ってわかりきってるから大丈夫だよ」
「お前らでなく周りにだ」
ばれるのも時間の問題じゃない? って言うのはさすがに黙っておいた。
リアス様はカリナに目を向けて、聞く。
「それで、とくに欲しいものがない場合はどうすればいい?」
「んー……。後日買い物に出たときに気に入ったものを買うか、ですかね」
「でもリアス様、そんなに”欲しい”って言うものなくない…?」
「それですよね。行っても決まらなさそうですわ」
「俺が欲しいのは物でなくてクリスティアが喜ぶ顔だしな」
わぉ突然のデレいただきました。
びっくりしてリアス様を見ると、当然というように肩を竦める。
「だから自分のは別にない」
「ここぞとばかりにイケメン力を出しますねあなた……」
「恋人の笑顔以上に欲しいものなんて無いだろ」
「どうしてリアス様は不意打ちでそういうこと言うのっ…」
「クリス胸押さえちゃったよ」
ときめきという名の胸の苦しさが止まらないんだもの。
「で、見つからない場合は引き直しをしても?」
「あなたがいいならそれでもかまいませんが」
「あ、それかクリスの望むものは? 喜ぶ顔が見たいならそれもアリじゃない?」
「あら、いいじゃないですか」
え? さらにイケメン力を出させてわたしを殺す気ですか??
「クリスティア」
なんて胸を押さえてたらリアス様の声が聞こえて、そっちを見る。
ほほえんでたリアス様は首を傾げて。
「何か欲しいものはあるか?」
だっめだ果てしないイケメン力に死にそう。
なにこの人。やばい。語彙力なくなってきた。
思わず顔を覆ってしまう。
「照れちゃったね」
「”可愛い”には照れないのにな」
「言われ慣れたんでしょう」
その通り。
「それで? 欲しいものは?」
自分の手で真っ暗な中で、リアス様の言葉に必死に頭を回転させる。
欲しいもの。買えるもので。
ぽろっと「リアス様」なんて口から出そうだけど買えるもの。
「えっと」
「ん?」
「、あ…」
「あ?」
「あ、あるばむ…?」
回転させた結果ものすごい無難なものにしてしまった。
「アルバムですか」
「そういえば残り数ページだったな」
「ん…」
「夏写真撮るだろうし、少ないなら早めに買っちゃってもいいかもね」
「ん…」
「クリス語彙力が」
だっていけめんすぎて。
「お前がいいならそれにするが?」
「いい…それがいい…」
「じゃあそれで」
「今度学校帰りに買いに行こっか」
「人が少なければな。お前のゲームもあるし」
「そーね。まぁ無理ならネットでいいよ」
「あぁ」
「彼氏様はイケメンですねぇ」
リアス様とレグナが話してる中で、いつの間にか隣に寄ってきたらしいカリナの声が耳元で聞こえた。顔から手を離して見たら、隣でものすごくにやにやしてて。絶対楽しんでる。まぁうそついても仕方ないので。
「…ほんとに…とても困る…」
「表情変わってないですけどね」
「今とても感謝してます…」
「ふふ、クリスったらかわいい」
わたしの頭をなでながら「よかったですね」って言うカリナにうなずいた。楽しそうに笑ってから、カリナはまだ話してる男子組に声をかける。
「リアスも一つ決まり、クリスは悶えてることですし……レグナ、小休憩ということで女王様の命令使ってみたらいかがです?」
それに、二人がこっち向いた。わたしの状態を見て、レグナは笑ってうなずく。
「ってもなんかあるかな」
「言われると難しいよな」
「ねー」
首を傾げながら、レグナが悩む。
見守ること数分。その間に深呼吸をして、落ち着いた頃。
ぱっと、楽しそうな顔をした。
「決まりました?」
「せっかくだから王様ゲームっぽくしようよ」
「あの王様だーれだってやつ…?」
「そうそう。して欲しいことはぱっと浮かばないし。ちょっとした休憩にはもってこいでしょ」
「いいじゃないですか」
「それで? お前が常に女王か?」
「うん、まぁもう名称はなんでもいいわ」
文句を言うことに疲れたらしいレグナは、そこだけ死んだような目でうなずいて。近くに置いてたメモ帳に数字を書いて、元々お仕置きボックスだった箱に入れる。
「はい、んじゃ1から3の数字入れたから引いて」
言われたとおり、順番にボックスから紙を引いた。
わたしは「2」。
「おっけー?」
「ああ」
「引いた…」
「そしたらー、どうしよっかな」
んーってうなってから、笑う。
「1番が2番の膝の上に乗る、とか?」
「2番、わたし…」
「俺が1番だな」
待ってつぶれる。
「え、1番の膝の上に乗るんじゃなくて…?」
「1番が膝の上に乗るらしいな。女王の命令だと」
「まじですか…」
「クリスティアつぶれません?」
「そこまでは重くないが?」
「いやサイズが違いすぎていろいろクリスティアの負担がでかすぎるでしょ」
「言っておくがその命令を出したのはお前だからな」
「定番かなと思ったらちょっとミスった」
ミスりすぎにも程がある。
「あなたが抜けてることで女子二人に男子一人ですからね。膝の上に乗るだとか体重やサイズに関わるものは厳しいかもしれませんわ」
「だよね。変えよっか」
「リアス様がどうしても乗りたいならがんばる…」
「逆なら大歓迎だが今回のは俺も願い下げたい」
たしかに絵面はひどそう。あとリアス様の精神的にも。
まぁ一回免除みたいな感じだからラッキーってことにさせてもらおう。
「では一度引き直しですかね」
「番号わかっちゃってるからね…」
「はいじゃあ戻してー」
仕切り直しで、引いた紙を戻して、もう一回引く。次は──1。今度はまともなものを。もしくはスルーを。
願いを込めて見たレグナは少し悩んでから、口を開く。
「じゃあ3番が暴露話」
わぁいスルー。そして当たったのは隣のヒト。
「3番……また俺か」
「なにかあります?」
「このメンバーで暴露することも──あぁ」
あごに手を添えたリアス様がそういえばって顔をして。
「レグナの腰を触ったな」
なんつー暴露してんのこの人。
「あー、一緒に就寝のときの」
「え、意図的に…?」
「んなわけあるか。癖で」
「あなた腰を触る癖なんてあったんですか変態ですね」
「そっちじゃねぇよクリスティアを触る癖」
たしかにあなたわたしのことよく触りますけども。
まさかほんとにこっちでくっつくのと若干疑いの目で見ると、二人して違う違うって首を振る。
「クリスティアとしか基本寝ないから、レグナが動いたときに反射的に」
「そうそう。”クリスティア?” って腰引き寄せながら聞いてきたから”おわっふレグナです”って名乗っといた」
おわっふまで再現してカリナと吹いちゃったじゃん。
「暴露できるものと言ったらこのくらいだな」
「十分ですわ……ふふっ」
「おわっふ…っ」
「肩びくつかせた後何事もなかったかのように律儀に名乗るからなお笑うよな」
「めっちゃくちゃ布団震えてたよね」
「その中でお前はさっさと寝たな」
目に見える。
「さて、暴露は女王を巻き込むようなものしかなかったが。満足か?」
一通りカリナと笑ったのを見計らってリアス様が聞くと、レグナはうなずいた。
「とりあえずね。今んところもうネタ思い浮かばないし、他の消化もあるからここで切り上げでいいや」
「では次に行きましょうか。あとはクリスとリアスのお願い事カードですよね」
言われて、さっきとは打って変わってわたしとリアス様は二人して少し困った雰囲気になる。
「これはこれで決まってないんだよな……」
「わたしも…今日やることじゃなきゃだめ…?」
首を傾げたら、カリナはいつもみたいに優しく笑って、「いいえ」って首を振った。
「内容だけ今日中に決めてくだされば、実行日はずらしてかまいませんわ。せっかくのご褒美ですもの」
ずらしてもいい…。あ、じゃあ。
「お出かけ、とかでもいいの…?」
言ったとたん、リアス様が止まったのがわかった。それはもう”ピシッ”て効果音が似合うくらいに。
「あら、もちろんいいですよ」
「本気か……?」
「リアスがひきこもりが外に出されるときみたいな絶望顔してるぞ」
「そりゃなるだろう……」
「でも、貸し切りなら、いいんでしょ…?」
あ、目そらされた。あれ、だめだった?
「四月はこわかったってなってたけど…一昨日のお風呂、絶対行かないとは言わなかった…」
だから四人で貸し切りならいいのかな、って。
首を傾げて聞くと、リアス様はすごい悩んだ顔してる。苦渋の決断って感じ。え、いいかなと思ったけど違ったかな。だめか。
「えと、だめなら、別にいい…」
さすがに無理はさせたくないし。
あ、そうだ一昨日のプールってことにすればいいかもしれない。未だに悩んでるリアス様にそう、言おうとしたところで。
「今からなら、全貸し切りで旅行プランができますけれど」
口を開いたのは、カリナ。全員で見て、どういうことって首を傾げる。
「……は?」
「プールのついででよければ旅行プランができますよ?」
「待て出かけるから話が飛躍しすぎてないか」
「けれどあなたにとって楽じゃありません? 二回もどこかにというわけでなく、一括ですべて収まりますわ」
「確かにそうだが」
「さすがに一昨日のプールをそのまま彼女のお願いに、というのはあなただって嫌でしょう?」
リアス様がぐって押し黙る。ねぇカリナそんなしなくていいよ。けれど言うひまもなく、カリナのプレゼンが続いてく。
「ただどこで、というのは明確にまだ決められませんが……とりあえず今オッケーを出してくだされば、夏に行く場所の全貸し切りは可能だと思いますわ。移動も送迎でもいいですし、テレポートでも可能でしょう。一切他の方が入らないという環境は作れるかと」
そこまで聞いて、リアス様の表情が少しだけやわらいだ。
「……一切?」
「えぇ、一切」
「「……」」
じっと見つめ合って、しばらく。
リアス様の目が、今度はわたしに向く。ちょっとだけまだ、悩んではいるけれど、
「…………………………わかったよ」
わたしの目の行きたいって主張激しかったのか。深く深くため息をついてから、ひとまずオッケーいただきました。
「ありがとっ…」
「っと」
うれしくて、リアス様に抱きつく。
「では計画は後々決めるということで」
「楽しみだねクリス」
「うんっ…」
仕方ないなって笑いながら頭をなでてくれるリアス様に、もう一回ぎゅって抱きついて。
「そうだ…」
「ん?」
「お礼…」
体を離して、リアス様が引いたお願いごとカードを持つ。
「お礼に、なんでも聞く…」
目を少しだけ開いたリアス様より先に、カリナたちが嬉しそうな声を上げた。
「よかったじゃないですかリアス」
「頑張る分の対価としては相当良いものじゃん」
「……何でもと言われても大抵のことは叶ってる気はするんだが」
わたしの腰に手を添えて悩む。たしかにいろいろ自分で叶えていらっしゃるけども。
「なんか、ない…?」
「何か、なぁ……」
首を傾げて悩んでいたら横から思わぬ提案が。
「せっかくなら恋人特権でできることにしたら?」
え。
と、言ってきたレグナを見る。
「別にキスとかじゃなくてもなんかない? 特権的なの」
「えぇ…」
なんかあったっけ。恋人特権って言ったらそういうスキンシップ的なものしか浮かばないんだけど。
どうしよう、ってつい癖で。助けを求めるようにリアス様を見た。目が合った瞬間に、少し困った顔。
「……恋人特権と言われるとそういうスキンシップしか浮かばないんだが」
「うん、言っといてなんだけど俺もだったわ」
なんで提案したのレグナ。
二人して困った顔してたら、今度はカリナの声が聞こえた。
「ひとまず恋人特権というのは置いておきましょうか。お二人だけの特別というもので考えていきましょう」
「二人だけ…?」
二人だけって言われたら。
「額、合わせるの…?」
「だろうな」
自然と二人で、額を合わせて。
近くなった紅い目と、見つめ合う。
…うん。
「いつも通り過ぎて特別感がないな」
「リアス様も思った…?」
ほとんど毎日やるもんね。
ちょっと隣でパシャって音聞こえたんだけど。カリナでしょ。
「またコスプレでもする…?」
「さっきので十分だしな……」
「これ以外でお二人で特別なものとかは」
「……特にないな?」
「たぶん…」
近い距離のまま思い返してみるけど、うん、特別っていう感じのはないかもしれない。
また、悩む。
横からレグナたちのうなり声も聞こえた。
そうして四人で悩んでいたら。
「あぁ」
リアス様が、声を上げた。
間近にある紅い目を見て、少し首を傾げる。
「なにかありました?」
「いや、ないなら増やせばいいじゃないかと思って」
増やす?
よくわからないでいると、リアス様は体を離した。
少し遠くなった紅い目が、まっすぐわたしを見て。
「とりあえずその願い事カード、お前のできる範囲なら何でもしてくれるんだな?」
そう、聞いてきた。
一瞬きょとんとしたけれど。
「そりゃもちろん…」
できる範囲でなら、当然。
しっかりうなずくと、「なら」ってリアス様は身を寄せてきた。
「なにするの…?」
「頬貸せ」
「?」
近づいてきてる間に言われた言葉に従って、軽く右のほっぺを突き出すように頭を傾けた。
「ん…」
直後。
「…!」
あったかい感触。
やわらかい、けれど。よくある唇でしたじゃないことはすぐわかった。知ってる感触だったから。ヒュウってレグナが口笛鳴らしたのを聞きながらたしかめるように目を横に動かしたら、やっぱり頭の後ろが見えて。リアス様とわたしのほっぺがくっついてる状態に安心して、思わぬことに上がってしまった肩の力を抜こうとしたら、
「っ?」
触れあった反対側のわたしのほっぺに手を添えて、目の前の人が動いた。
なんと恋人様。
合わさってるほっぺにすり寄るように、顔を、動かしていらっしゃる。
いやすり寄るようにっていうか、
すり寄っていらっしゃる。
「あ、あの、リアス様…?」
「なんでもしてくれるんだろう?」
いやそうなんですけれどそんな甘い声で耳元でささやかないで。不意打ちの低音に、また肩が跳ねた。
「……悪い」
リアス様はそれを怖がったって取ったのか、一旦動くのはやめて。びくってしたわたしを安心させるように抱きしめる。
別に怖がったわけではないので、平気って伝えるように、わたしもリアス様を抱きしめた。
「……」
大丈夫ってわかったリアス様は、またすり寄ってくる。
肌がこすれる音を聞きながら、リアス様に集中した。
──あったかい。
肌がすべすべしてる。
ときどき当たる髪の毛が、ちょっとだけくすぐったい。
こうして、いとおしいって言うように触れられることが、うれしい。
うれしくて、幸せで。自然と、自分のほっぺがゆるんだ。
「……」
──ねぇ。
体温を感じながら、思う。
「…」
あなたも幸せな表情を、してくれていますか。
わたしに触れることで、うれしいとか、そういう気持ちを。感じてくれていますか。
それを知るために、あなたの顔が、見たい──。
しかしわたしは今現在リアス様と向かい合っておりまして。
お顔を拝見することは叶わないわけでして。
ただやっぱり顔を見たいというのは捨てられない思いでして。
かくなる上は。
「カリナ、写真っ」
「お任せあれっ!」
言った瞬間にパシャパシャ後ろで音が鳴る。ナイスカリナ。でもよくそんなすぐに音鳴ると思わなかったよ。一秒かかってないよね絶対さっき撮ったときから動かずにいたでしょ。あとで送ってね。
「あ…」
そう思った矢先に、離れてく体温。
「リアスさまー…?」
「もう十分だ。それとさすがに写真は俺が死にたくなる」
しまったこっそり頼めばよかった。
「かわいかったねリアス」
「うるさい」
しっかり見てたレグナはほほえましく言う。ずるい。
「見たかった…」
「大丈夫ですわクリスティア。奇跡的にきれいに写ったものがあります」
「どれ」
カリナに言われて、差し出された写真を食い気味に見る。
そこに、写っていたのは。
「わぁ…」
とても満足そうにわたしのほっぺにすり寄ってるリアス様。
え、最高では??
「おいくらですか…」
「金を払おうとするんじゃない」
いやこれには相応の対価が必要。
ねぇ、ってカリナの服の裾を引っ張ると、にっこり、かわいらしく笑った。
「クリスがかわいらしい格好をしたら差し上げますわ」
「お前もノるな」
「レグナ服作って。アレンジ可」
「喜んで」
「なんだその無駄な結束力は……」
ため息をつくリアス様だけど、どうせあとでその写真送ってもらうのわかってるからね。
「では服を作るとなると後日になりますが。とびきりかわいいお姿、期待していますわ」
「「任せて」」
レグナと揃って親指を立てる。
というわけで、新たに誰にってわけじゃないごほうびが追加されて、ごほうびタイム終了。
『後日送られた写真は、控えめに言って最高でした』/クリスティア
「泊まっていかないの…?」
あれからレグナが持ってきたテレビゲームをやったり、ちょくちょくレグナの女王タイムで遊んだりして、午後六時。
良い時間だし帰ると言い出した双子に玄関先でクリスティアが聞くと、カリナは微笑んで頷く。
「泊まっていこうかなとは思っていたんですが。よくよく考えたら制服やら鞄やらはすべて家なんですよね」
「あれだけ荷物を持ってきておいてか」
「あれは全部ゲームとか」
「嘘だろう……?」
「…」
自分でもわかるくらい信じられないという顔をしている俺とは違い、てっきり泊まってくと思っていたクリスティアは少し残念そうだ。それに気づいたカリナが、彼女に目線を合わせて言う。
「またこういうお泊まり、いつでもできますから。ね?」
いやいやいや。
「許可してないんだが?」
「かわいい恋人のお願いですよ、叶えてあげなさいな」
「旅行で手一杯だ」
「まぁリアスのことは任せてください。いい感じに丸め込んでおくので」
おい待て。
「丸め込むって何だ」
「では帰りましょうかレグナ」
「頼むから聞いてくれ」
「じゃあまた明日ねー」
「また明日…」
「おやすみなさい」
「……はぁ、おやすみ」
いつも通り話を聞かないカリナに溜息を吐きながら、歩き出す双子の背を見送る。
その姿が見えなくなってから家に入り、ドアを閉めた。
「楽しかったね…」
「……まぁ、なんだかんだな」
大半は俺とレグナの精神修行みたいなものだったが。全体を通して、楽しくなかったと言えば嘘になる。
靴を脱ぎつつ、「また泊まりにくるから」と言って置いていった大半の荷物を見て。あっという間に過ぎていったゴールデンウィークを思い返した。
主にレグナが騒いでいたトランプ大会に、最初は不安があったがある意味新鮮だったスゴロク、味方のクリスティアに無駄に動揺させられたゲーム大会、珍しくカリナの提案が当たりで斬新だったチェス。
可愛い姿を見れた罰消化の時間。
「……──。」
そうして、今日の褒美のところまで思い返して。
親友が言った言葉が、脳裏に響いた。
”恋人特権”。
未だに、自分にはないもの。
同居は特権と言えば特権かもしれないが、長い時間、恋人と同時に兄妹のように過ごしてきた自分達にとっては、”恋人特権”と言うほどじゃない。
俺が認識する”特権”は、恋人間でしか、できないようなこと。
キスだったり、それ以上だったり。
まだ、許されていない領域。
「っ?」
できないことが、悔しいわけじゃない。けれど、気づいたときには、部屋に戻ろうとするクリスティアの腕を掴んでいた。
「リアス様…?」
振り返ったクリスティアは不思議そうに首を傾げる。
何も疑っていない、整った、綺麗めで、けれど可愛い顔。
「どうしたの…?」
小さな、口。
──あぁ、これが魔が差すというものか。
「え──」
少しだけ力を入れて、腕を引っ張る。
突然のそれに対応しきれず、彼女は俺の方に傾いてきた。
その首を支えるように手を添えて。
唇を、近付ける。
あと数センチ──。
あの頃からしたかったこと。今の今まで、できないこと。もしかしたら、できるかもしれない。
なんて思って。更に、唇を近付けたときだった。
「、っ…」
自分の身を支えるようにして俺の肩に置いていた彼女の手に、力が入った。
グッと、服を引きちぎらんばかりの強さ。
それに、沸き上がった熱が一気に冷めて。
「……」
我に、返った。
──俺は今何をしているんだろうか。
そんな、落ち着いてきた思考でした自問にはすぐ答えられてしまうわけで。
あぁ、やらかしたと、そっと、近付けていた顔を離した。
「っ…」
そこには、固く目を瞑り、カタカタと震えているクリスティア。
一気に罪悪感が押し寄せる。
「……悪かった」
そう言うと、彼女はゆっくりと目を開けた。
涙を溜めた蒼い瞳で、俺を見上げてくる。
その瞳の中に見えるのは、不安、恐怖。
恐らく、いつものように触れようとしたら怖がらせるだろう。それは何千という付き合いの中で嫌と言うほど知っている。
ひとまず、害はないと言うように両手を緩く上げた。
「何もしない」
押さえつけることなどせず、逃げ場を作った状態でそう言ってやれば。
「、…」
ほっと、彼女の肩の力が抜けた。それを確認してから、やっと手を伸ばす。
「…」
怖がらせないよう、ゆっくり、ゆっくりと頬に手を添える。今度は、怯えた表情は見せなかった。
ひとまず安堵の息を吐き、添えた手を首に回し。心音を聞かせるように、抱きしめて。
「……大丈夫だから」
優しく、壊れ物を扱うように、頭を撫でた。
「…」
完全に害はないとわかったのか、腕の中の少女のような恋人は、手の力も緩めていき。
時間を掛けて、俺に体重を預けてきた。倒れないように足に力を入れて、頭を撫で続ける。
沈黙の中、そうしていると。
「…ごめんなさい」
小さな声で、彼女が言った。
「……謝ることないだろ」
「だって、わたしのせいで、がまんさせてる…」
「別に我慢は──」
いやしているな。とくにこの同居生活を始めてから。男というものは大変だとやっと知ったくらいだしな。
そこは置いておいて。
「…ごめんなさい…」
一瞬の沈黙を肯定と取り再び謝ってくるクリスティアに。
「……お前が悪いわけじゃない」
努めて、優しく言った。
事の発端は、この長い人生が始まって半分くらい経った頃だろうか。
二人で世話になっていた王宮に、まぁ大層女好きの王子がいたもので。女好きと言えばもうわかるだろう、クリスティアにも当然ちょっかいをかけていた。
もちろん彼女は俺以外に興味がなかったので、その王子のことはガン無視。それに俺も傍にいることが多かったし、結果を言ってしまえば、幸いなことに体に被害はなかった。
が、余計な恐怖心を植え付けられた。
ある日、クリスティアはその王子が嫌がるメイドを引っ張って歩いていたのを見たそうで。あれよあれよと言う間に、メイドは部屋に連れ込まれたらしい。
とても勇敢な彼女はもちろん助けに行った。そこまではよかった。イケメンだなと称えてもいい。問題は次だ。
そうして行った部屋のドアを開けて、クリスティアの目に飛び込んできたものは、
いやらしく腰を振って、メイドを誘っている王子だったそうで。
服は着たまま。嫌がっているメイドに、まぁなんだ、今夜どうだみたいなことを、その、そういう場所を押しつけている状態だったようで。
恐らく俺や双子、他の奴らが見たら何してんだこの王子はとすかさず扉を閉めるか物を投げつけて中断したかしただろう。
けれど、幼い頃から”そういうこと”に話程度にしか触れてこなかった彼女には、刺激が強かったらしく。
その王子を見て、本能的に危険を察知したんだろう。もしかしたら自分もああされるかもしれないと。
いくら服を着ているとはいえ盛っている奴を見たのは初めてで。性交渉とは互いに愛し合うものだと認識してきた少女のような恋人に、その光景は恐怖心を植え付けるには十分だった。
俺が行った頃には顔は真っ青。挙げ句の果てには吐いたほど拒絶反応を起こし。
それ以来、彼女は恋人特有のスキンシップができなくなった。
元々できていたわけじゃないが、昔は進もうかとなれば恥ずかしがっていた方だった。乗り越えるまで別に急ぐわけでもないしなと彼女のペースに合わせていたのが仇になったと思う。
それがあってからは、恐怖で体を震わせるようになってしまった。俺が触れようとしてもだ。
さすがに恋人に触れられないのは俺だってきついし、いざというとき、それこそ危ないからと手を取ろうとしたときに拒絶されても大変困る。そこからは長い長い時間をかけて、やっと。額を合わせるまで近づいたり、抱きしめたりができるまで戻した。
恐らく下心を宿した目が苦手なんだろうと当たりをつけて、自分だけは害はないと、必死に下心は隠してきた。
そうしなければならなくなったのは彼女のせいなんかではなく、死んでもなお、恐怖心を植え付けているその王子のせいなわけで。
しかも今回は、俺がそれを引き起こさせてしまったわけで。
「お前は何も悪くない。特に今日は、俺が悪い」
「…」
謝罪を込めて、緩く背を叩きながらこぼす。けれどふるふると首を横に振られて。
これはまた、昔と同じで堂々巡りだなと苦笑いをこぼした。そうして結果は彼女に自己嫌悪をさせて終わる。さすがに運命の日以外、何度も同じ失敗をする気はない。
ここで話を切り上げようかと、声を掛けようとしたときだった。
「…ねぇ」
「ん?」
先に彼女が言葉を発し、開き掛けた口を閉じる。ゆっくりと身を離したクリスティアは、悲しげに眉を下げて、問うてきた。
「す、ぐじゃなきゃ、だめ…?」
……すぐ?
「……そういうこと?」
「…」
小さく、頷く。
……まぁ、すぐにできるのに越したことはないんだろうが。今日はあの言葉があったから魔が差してしまっただけなので。
首を、横に振った。
「……お前に無理をさせてまですぐにとは思わない」
「…」
「怖がらせてまでする気はない」
「…」
いやほんの数刻前に思いっきり怖がらせたんだが。我に返ったからセーフにしよう。あれは今日の話があったからいけない。
「あの、ね…」
そんな心の中の言い訳は、服を引っ張られたことによって中断された。
「ん?」
「えと…」
視線を彷徨わせながらも必死に何かを言おうとしているクリスティア。ひとまず威圧にならないよう、目線を合わせるようにしゃがむ。
「どうした」
優しく聞いてやると、ふらふらと左右を彷徨っていた瞳は、しばらくして意を決したように俺を見た。
「手…」
「手?」
「手、貸して…」
言われるがまま、利き手の左を差し出した。その手を取った彼女は、ゆっくりと、自分の顔に近付けていく。
辿り着いた先は、クリスティアの頬。
包み込むようにして、添えられた。
何かと思って見ていれば。
「!」
すり、と。
俺の手に、頬をすりつけてきた。
昼間、俺がしたように。
ただ、昼と違うのは。
「っ」
さりげなく、本当に微かに、唇を、当てていること。
口元に行くと、頬とは違う柔らかさを感じる。
それだけならただ単に「可愛らしい」で済んだのに。伏し目がち開いた瞳と、紅くなった頬がそれで済ませてくれない。
「…ふ」
「、……」
加えて吐かれる息もよろしくない。
好きな女がそんな扇状的な姿をしていたらそりゃ嫌でも意識は”そういうこと”にいってしまうわけで。
再び、体の中で熱が沸き上がるのを感じた。
これはだめだ。
「っ、クリス」
「あのっ」
そろそろ、と言い掛けたところで、遮られる。わざとなのか偶然なのか、手は唇が触れる場所。
「あのね」
緊張で吐いた息に、指が跳ねた。
俺の状態を気にするまで余裕がない彼女はまたうろうろと視線をさまよわせる。
「…」
そうして何度か右往左往したあと。
「……」
「…っ」
目が、合う。
その瞬間、クリスティアの肩が少し跳ねたことから、自分が”そういう目”をしているんだろうとわかってしまった。
内心舌打ちをして、手を引こうとするけれど。
「ま、って」
力を込めて、止められる。
「あのね」
喋る度に、手のひらに柔らかい感触が当たる。また、緊張の息を吐いて、じっと俺を見た。
勘弁してくれ。
そうは思うけれど。どうしても恋人に甘い俺は、彼女の言いたいことを止めたくなくて、じっとする。
「どうした」
「っ…」
コクリと動く喉の感覚さえも伝わり、熱が上がる感覚がする。
なんとか欲に飲み込まれまいと、奥歯を噛みしめた。
「…」
「……」
「…ま、だ」
永遠のように感じられる沈黙を、ゆっくり動いた彼女の口が破る。
「まだ、待ってて…」
目に涙を溜めて。恐怖に手や声を震わせながらも、それでもと言うように俺としっかり目を合わせて、言った。
「こ、わいけど、でもっ…、ちゃんと、し、したい、って、思ってる、から…」
だから、もう少し、待ってて。
掌に、唇を当てて。
見つめ合うこと数秒。それだけ言うと、するりと抜け出すようにして、廊下をパタパタと走って行ってしまった。
「……」
固まっている俺は、その背を見ているだけ。
廊下を曲がって見えなくなってから、ゆっくりと、先ほどのことを頭で反復する。
”待ってて。
したいと思っているから。”
そう言った。
直接的な言葉ではないけれど。
つまりは、”そういうこと”を、したいと。
理解した瞬間に、違う意味で、ブワッと体温が急上昇した。
「っ……」
小さな口で、一生懸命に伝えてきた言葉が、頭の中で駆けめぐる。
普段からあまり自分の気持ちを言わないクリスティア。それを言うことが苦手だから。
あいつが言い慣れないということは俺だって聞き慣れないわけで。
先ほど彼女の頬に添えていた手で口元を覆い、俯く。
恐らく間接的に唇が合わさっているが、今それを気にしたらやばいので、気づかなかったことにする。
深呼吸をして、今はどうにかこの激情を収めるよう努めた。
叶うなら、この感情に任せて今すぐいろいろしてしまいたい。彼女にはすぐには大丈夫と言ったけれど。
あんな煽るようなことをされたらそりゃスイッチだって入ってしまうわけで。
ただそれをした瞬間、今までの苦労も、この先触れ合う未来も全て消える。それだけは勘弁したいので、必死に抑えた。
「……はぁ」
何か違うこと。欲を逸らせるような違うこと。
素数を数えればいいんだったか。あとは運動? さすがに筋トレをいきなりし出したら逆に不信感を与えるな。一旦本でも読んで気を紛らわせるか。あぁそれが良いかもしれない。クリスティアにも何か読ませてればあいつだって──
と、深呼吸をしてほんの少しずつ落ち着いてきた頭で、気付く。
まずあいつが傍にいる時点で気を紛らわすことなどできないのではないか。
勝手にどこか行かないようにと気を配っているし、あいつ自身自由すぎていつこちらに突撃してくるかもわからない。加えて自分が過保護すぎて生活のほとんどの行動も一緒。風呂もだ。
そしてその風呂は、まだ入っていないのでこれから共に入るのである。
あぁ。
レグナの言葉を借りるならば詰んでいるかもしれない。
「……あ”ー……」
この状況で入るのはまずいだろ。いろんな意味で。さっきので気まずいのもあるしいろいろと収まっていないので本当にまずい。
かくなる上は。
ポケットに入れておいたスマホを取り出し、慣れた手つきで電話をかける。
あいつには頼りたくないが仕方ない。今回はあいつにしか任せられない。
電子音の後、至極嫌そうに電話に出た女に、第一声。
「カリナ、クリスティアと風呂に入ってくれないか……」
恐らく相当参った声をしていたんだろう。
今回ばかりは深く追求せず、「わかりました」と返事が返ってきた。
『結局泊まりになり、翌日四人で登校した』/リアス