

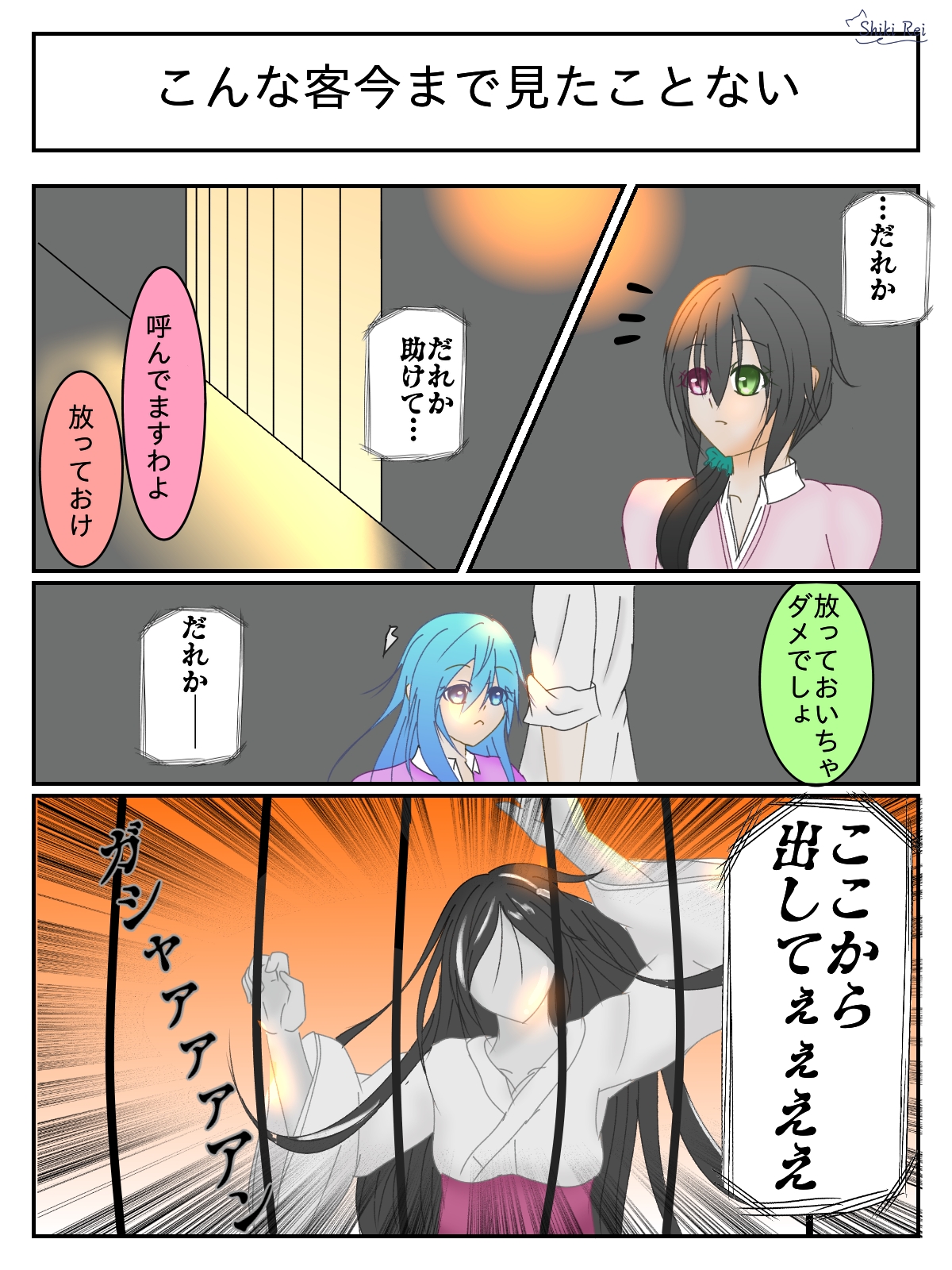
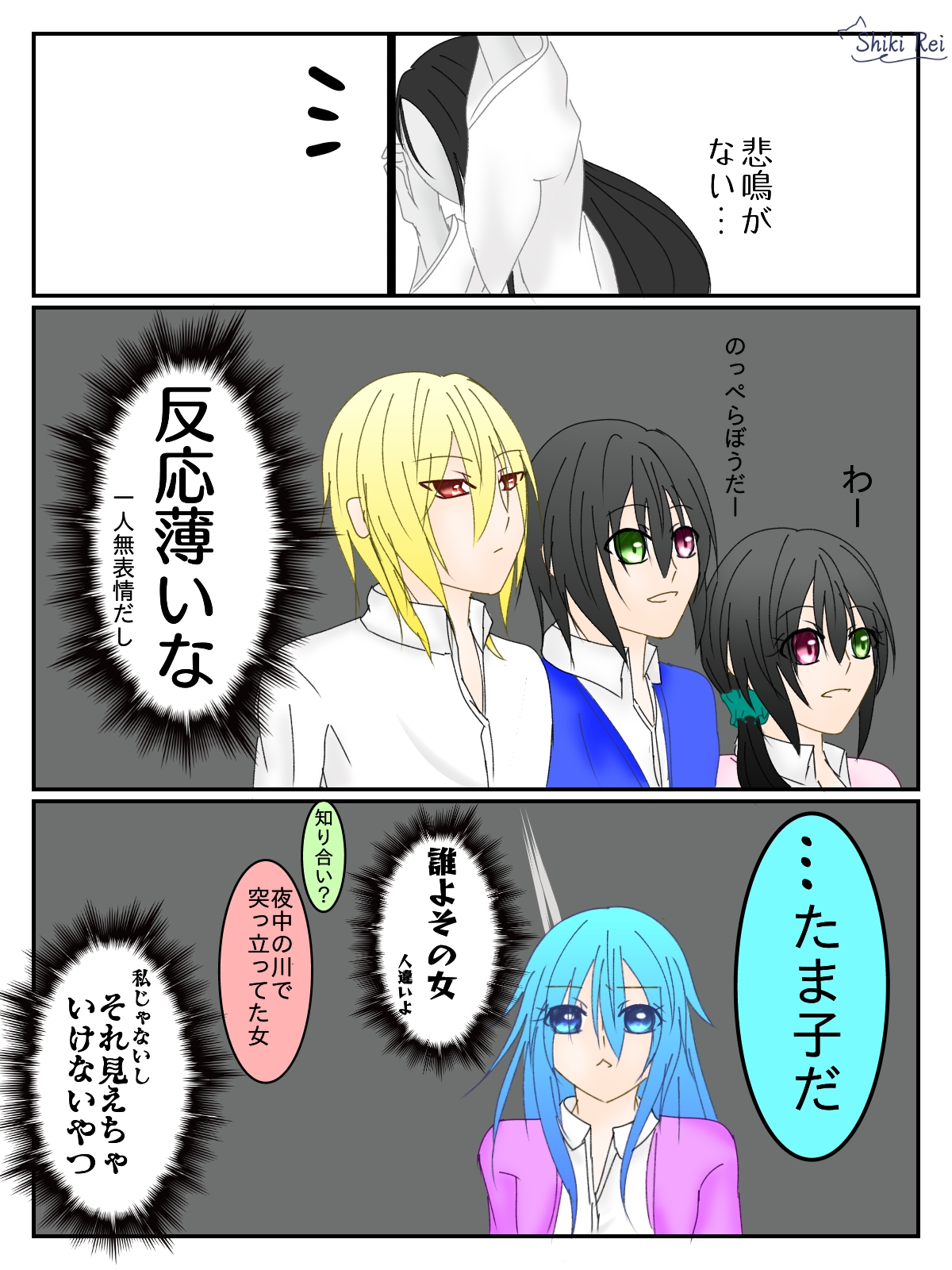

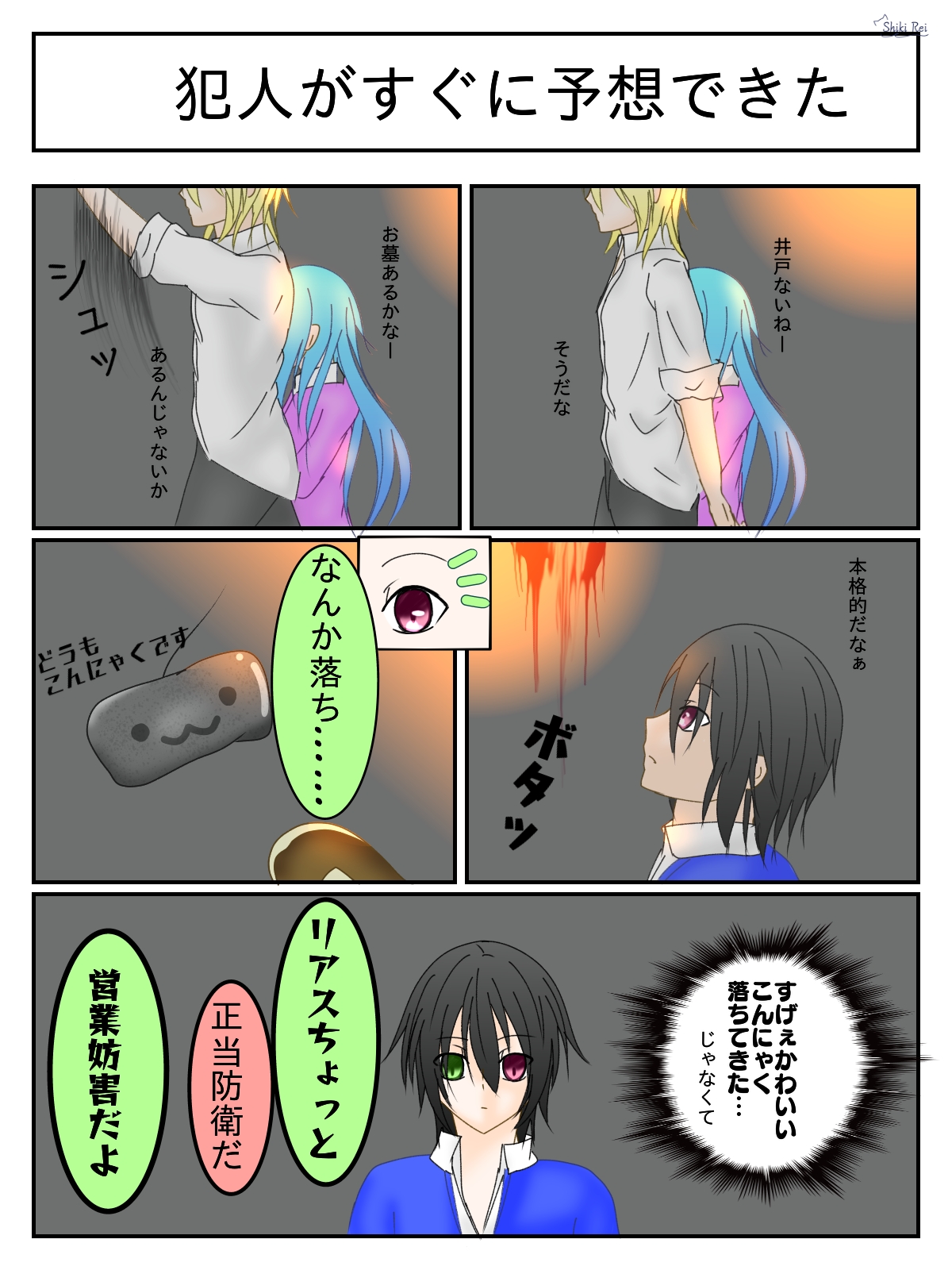


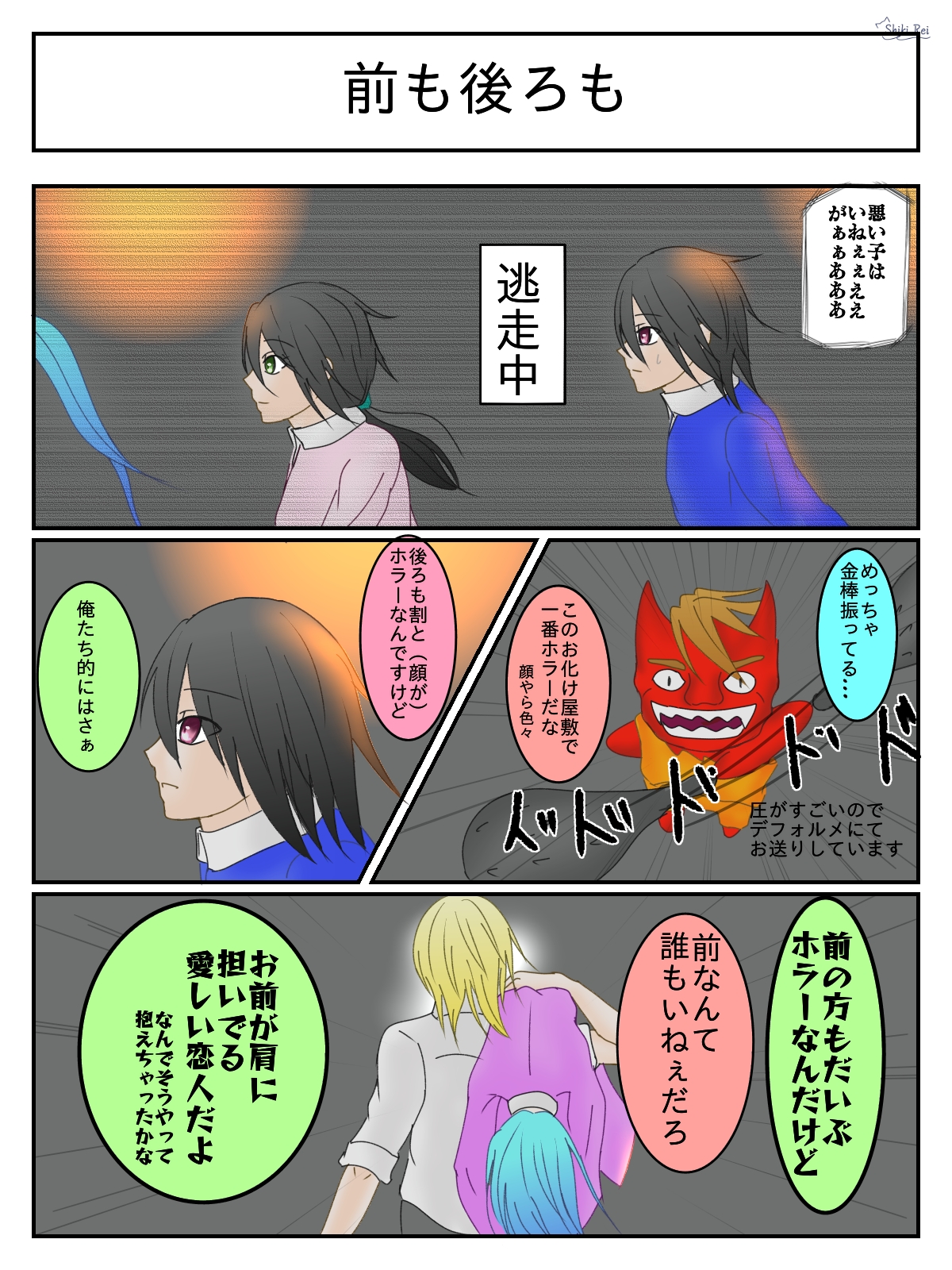
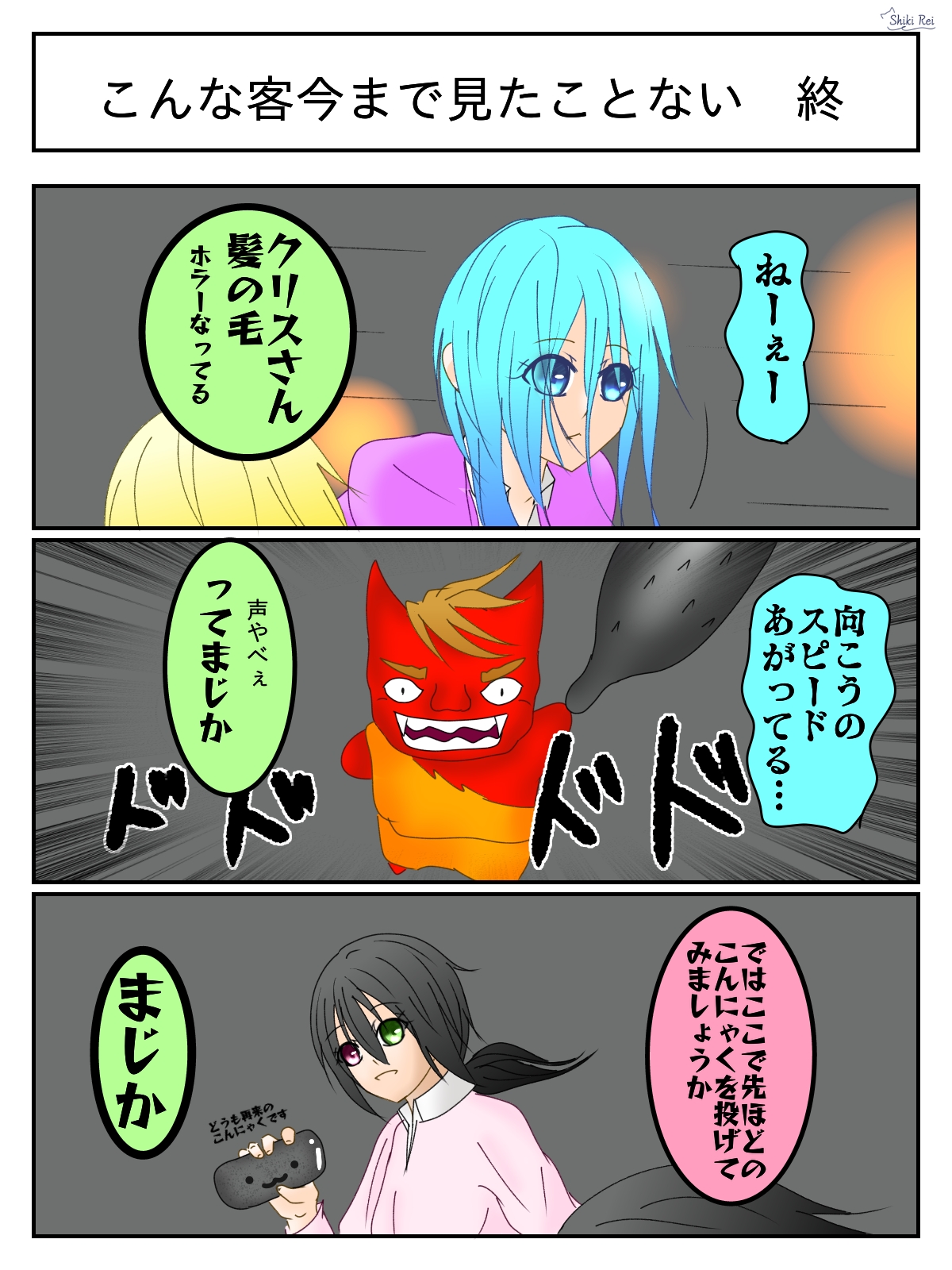


きれいな景色が好き。お花畑も、夕焼けも、星空も、海の中も。いろんな場所の、いろんな景色が好きだった。
「きれいだね…」
もう何年ぶりかもわからない、この観覧車の中の景色も。
「……悪くはないな」
観覧車から見下ろした景色につぶやけば、隣に座るリアス様もうなずいた。
お昼を食べて、園内のお菓子巡りをして。午後三時半くらい。集合時間が四時だから、アトラクションに乗るのはあと一つまでってなって、乗りたかった観覧車に来た。リアス様と並んで座って、だんだん遠くなっていく地上を眺める。ちょうど夕暮れ時で、景色がオレンジがかってすごくきれい。
「きれいなのはいいんですが、よかったんですの?」
窓に張り付くように景色を眺めていたら、前から声がした。目を向けたら、一緒に乗る双子がちょっとだけ申し訳なさそうな、気まずそうな顔をしてる。
「よかった、って…?」
「観覧車と言えば恋愛スポットでしょう?」
「リアスと二人で乗らなくて良かったのかなって」
双子としては四人で乗るのが申し訳なかったみたい。楽しいのに。それに、
「今更恋愛スポットだなんだで二人になりたいとせがむほど初々しくないが?」
「まぁ年数的には何千っていう付き合いだもんな……」
同じ意見のリアス様の言葉にうなずけば、レグナに呆れられた。もう何年だろう、三千? 四千? 正直あんまり覚えてないや。
「でもせっかくのお出かけですのに。リアスと二人きりの時間があまりなかったんじゃないです?」
「その二人きりになれるチャンスはお前がつぶさなかった?」
「それは今は置いておきましょう」
「そういえば行きは”手助けする”だとか言っていなかったか?」
「ちょっと予定変更がありましてですね。次回にご期待ください」
「いつだそれは」
「…ふふっ」
いつもの掛け合いに、思わず笑顔がこぼれる。その笑い声に、三人が一斉にこっちを向いた。
「あら楽しそうですわねクリスティア」
「…うん、とっても」
素直に伝えれば、三人の顔もほころぶ。それがまた、わたしの心を満たした。
そこで、わたしを見たときに外の景色が目に入ったらしいカリナが声を上げた。
「あ、頂上ですわよ」
「ほんとだ。やっぱ結構高いんだね」
全員窓の外を見る。きらきらして、とってもきれいな景色。それを見ながら、また話し出す三人の声に耳を傾けた。
「カップルだったらアレやるんですか?」
「”アレ”とは?」
「あの”あそこが私たちの住む町だね”みたいなのですよ」
「誰がやるか」
「つか言われてもわかんなくない?」
「なんて夢のない男性たちなんでしょう……」
あきれた声のカリナに、今度はレグナが聞く。
「カリナは恋人できたら言うの? ”あそこらへんが私住んでるところなんです”的な」
「言いませんよ、見えないし自分でもわからないでしょ」
「お前も一緒じゃねぇか」
「こいつの場合”あそこです”と言って、男がそうなんだと話にノったら”いやわからないでしょう”と突き落とすタイプだろう」
わかる気がする。
「あなた私をなんだと思ってるんですか」
「腹黒いドS」
「そこまでドSではないでしょう?」
「腹黒いことは認めちゃうんだ?」
大好きな景色を眺めながら、大好きな人たちの声を聞く。楽しそうに話す会話を聞いているこの瞬間が、なによりも幸せだった。リアス様と一緒にいるのももちろん大好き。でもやっぱりこの四人でいる瞬間が、大好き。
「ねぇ、クリス、私そんなにドSですか?」
声をかけられて、またそっちに目を向ける。カリナは納得行かなそうな声してるけど、表情は楽しそう。
「人をおちょくるのが好きだろうお前は」
リアス様も、あきれた顔してるけど声は楽しそうで。
「もちろんあなたやレグナをいじり倒すのは大好きですが」
「おい」
「Sっ気十分じゃね?」
レグナも、そんな二人をほほえましく見てる。それを見てるわたしの頬も自然とゆるんで、自分でもわかるくらい、いつもより穏やかな声で返した。
「…たぶん、Sだとは、思う」
「ほらぁ」
「えー」
四人で、笑いあう。カリナがいじって、リアス様がちょっと天然で、そこをレグナがツッコんで。わたしはそれを聞いて、時々その会話に入って。何気ない日常。その日常で見える何気ない景色は、いつも輝いて見えた。それがこの四人でいるからだって気づいたのは、もうだいぶ昔。
当たり前のようなこの日々が、わたしにとってかけがえのない大切な宝物。
「というかカリナは腹黒いの…?」
「らしいですわ」
「そこは否定なしなんだ?」
「自分でもわかってるんじゃないのか」
「あら、自分では純粋無垢だと思ってますが」
「どの口が言っている」
「心底信じられないみたいな顔しないでください」
ずっとずっと、この時間が続けばいいのにって、いつも思う。
でも、時は流れていっちゃうから。
「……あら」
一通り笑いあって、カリナが外に目を移す。
「もうそろそろ終わりですわね」
つぶやいた言葉に外を見れば、だいぶ地上が近づいてる。
この時間も、もう終わり。
「なんだかんだ結構楽しかったなぁ」
「悪くはなかったかもな」
「珍しいね」
「珍しいと言うが一応常に楽しいとは思っているぞ」
「顔に出ねぇんだよ」
「クリスはどうでした?」
「わたし…」
カリナに話を振られて、今日一日を振り返る。
リアス様が許可をくれて、連れてきてくれた遊園地。カリナと乗ったコーヒーカップ、レグナが大変そうだったお化け屋敷。そして、四人で乗った観覧車。みんなでお昼ご飯食べて、歩きながらおかしを食べて。騒いで、笑って。とてもとても、幸せな時間。
「…とっても、楽しかった」
思い返せば、自然と笑顔になれる。幸せいっぱいな気持ちで、笑顔で、伝えた。そしたらみんなも、また笑う。それを見て、わたしはもっと幸せな気持ちになった。
「よかったですわ」
「連れてきて良かったなリアス」
「……たまには、悪くない」
「じゃあ今度はゴールデンウィークにどこか出かけましょうか」
「”たまには”と言ったのが聞こえなかったか?」
「月に一回位はお出かけしましょうよ」
「この交流遠足からゴールデンウィークまで一週間もないんだが。急すぎるだろう」
「あ、地上に着きましたよ。降りましょう」
「聞け」
話してたらあっという間に地上に着いちゃった。レグナから先に降りて、最後がわたし。
「ほら」
リアス様が、手を差し伸べる。わたしだけにしてくれる、王子様みたいなエスコート。それが、たまらなくうれしい。
「リアス様」
その手に自分の手を重ねて、観覧車を降りるとき、名前を呼ぶ。
「なんだ」
そうしたらリアス様はきちんと目を見て、わたしの言葉を待ってくれる。だからわたしも、リアス様の目を見て、言える言葉を口にした。
「…ありがと」
精一杯の、笑顔で。大好きな景色を見せてくれたこと。大好きな人たちとの思い出を増やしてくれたこと。大好きなあなたと、幸せなこの時間を過ごせたこと。
「……今日は気が向いただけだ」
いろんな意味を含めて言えば、リアス様はちょっとだけ微笑んで、わたしの手を引いて歩き出す。出口では、カリナとレグナが待ってる。リアス様と二人並んで、わたしたちは双子の元へ向かった。
──幸せな時間は、あっという間。過ぎた時間はもう、戻ることはないけれど。四人で過ごした思い出は、いつまでも胸の中に。
『大好きなものは、大好きな人たちと共に。』/クリスティア
バスに乗りうるさく話しかけてくるカリナをガン無視しながら揺られること一時間弱。
笑守人で点呼を取ってから解散し、双子と別れ、楽しげに今日のことを話すクリスティアの声を聞きながら家に着いた。
鍵を開けて、クリスティアを先に入れさせてから自分も中に入り、後ろ手に鍵を閉める。
あぁ、限界だ。
「──!」
靴を脱いで上がろうとするクリスティアの腕を引き寄せた。
驚いているが今はそれどころじゃない。
引き寄せた勢いでこちらに来た彼女を、思い切り抱きしめた。
「……はー……」
情けなく震える手で強く抱きしめ、確かめるようにすり寄って、クリスティアの匂いを吸い込んで。
安堵から、足の力が抜けた。
ただそのまましゃがむと確実にクリスティアがけがをするので、ドアにもたれ掛かったままずるずると床に座り込む。
「…汚れちゃうよ…?」
「すぐ風呂に行く」
そ、と小さく耳元でこぼして、クリスティアは慣れたと言わんばかりに俺の髪をいじり始めた。
いつもなら俺も同じように髪をいじるが、今日はそんな余裕はなく。
クリスティアの左胸に耳が行くように、すり寄って目を閉じた。
心底怖かった。
いくら笑守人の人間だけとは言え、人混みはやはり怖い。ましてや能力者の集まりで。同胞達を疑うのは嫌だがこればかりは仕方ないと自分に言い訳しておく。頭に植え付けられた恐怖は中々消えない。また傷つけられるのではないか。もしかしたら救えないんじゃないか。杞憂だとはわかっていても心のどこかでずっと不安だった。
そうして帰ってきてこのざまである。
情けない。
不甲斐なさに自分を叱咤したいところだがそれは彼女が寝てからにして。
まずは自分を落ち着かせることが先決だと、再び彼女の匂いを肺いっぱいに吸い込んだ。深呼吸をしながら、とくとくと生きていることを主張する小さな音を聞く。それ以上先に行けないとは知りつつもさらにすり寄った。
規則正しく上下する胸が、心地よく眠気を誘ってくる。
「……」
「……」
音を聞いている間、クリスティアは何も言わない。ただ黙って、俺の髪をいじり続けていた。
長くもないが、そう短くもない時間、そうしていると。
音に、彼女の感触に。段々と心が落ち着いて。
やっと、肩の力が抜けていった。
ほっと息を吐いて、思う。
……これ端から見たらすごい光景じゃないか。
玄関先で恋人を抱きしめて匂い嗅ぐとか変態か? しかも自分よりも幾分も小さい少女のような恋人を抱きしめて。ほんとにこいつ小さすぎて自分の犯罪感がやばい。同い年なのに色々やばいことしているんじゃないかという気になる。
仮にここでそういうことをしたら、もう自分でも認めざるを得ないくらい変態だと思う。さすがにしないが。そもそもこいつはまだそういうことができないが。
さて俺は何を考えていたんだったか?
さっきまで不安だったのが嘘のように思考が違う方向へ行ってしまった気がする。不安から抜け出せたから結果オーライと言うことにしておこうか。
そこで、小さくスマホが鳴った。そろそろバカな思考から戻ってこいとのお告げかとポケットから取り出し、クリスティアの肩に顎を乗せて、画面を見た。”写真を送信しました”とのポップが表示されている。送り主はグループ。言わずもがなあの双子。
スマホのロックを解除してメサージュのアイコンを見ると、二十五、六と件数が増えていく。あいつらどれだけ撮ったんだ。ピコピコと通知音がうるさくて、ひとまず通知だけでもOFFにしようと双子とのトーク画面を開いた。その合間に、まだまだ送られてくる写真が目に映る。
思わず、通知をOFFにすることを忘れて見入っていた。
昼時の写真から始まり、俺の腕を引っ張るクリスティア、カリナとクリスティアが地図を見て楽しそうに行き先を決めているものや、レグナと俺が辺りを見回しているもの。これ迷ったときのやつだな。方向が真逆でレグナとここどこだと見回していたのを思い出す。
他にも、菓子を頬張るクリスティアに、嬉々として観覧車に走っていくクリスティアを俺が追いかけていく写真。帰り際の、クリスティアの写真。遡れば行きのバスの写真や動画もある。動画は後で見るとして、ガーッとスクロールし、写真を見ていった。
「……」
写真の中にいるクリスティアは、どれも楽しそうだった。幸せそうで、普段あまり表情が豊かでない彼女の口角が、ずっと上がっていた。
その傍にいる、俺も。
「……クリスティア」
「なーにー」
髪いじりをしている手を中断させて、少し体を離す。不思議そうに見上げてくるクリスティアに。
「……楽しかったか」
そう、聞いた。
彼女は二、三度パチパチと瞬きしてから、告げる。
「とっても」
視界の端に映る、スマホの中の写真と同じ、とても幸せそうな笑顔で。
「……そうか」
再び引き寄せて、彼女の肩に頭を乗せた。息を吸い込んで、吐いたとき。
今日だけじゃない、今までの不安も、少しだけ吐き出された気がした。
俺が不安で遠ざけていた出来事。
彼女から奪ってしまった、大切なもの。
それを、一歩踏み出して与えたことで、愛しい彼女はこんなにも幸せな顔をするのか。
幸せそうに、愛おしそうに。俺が愛した笑顔で、笑ってくれた。
心が満たされていく。
同時に、ある思いも生まれた。
また、こうして一歩踏み出せたなら。
お前は同じように笑ってくれるのかと。
生物とは、欲張りで。一度良いことがあったのならもう一度、と思ってしまう。
欲張ってもいいだろうか。
まだ、口に出すことは怖いけれど。
約束は心に秘めて、強く抱きしめる。
「クリスティア」
「はぁい」
できない代わりに、伝えられること。
彼女が愛する思い出を、また一つ。
「俺も、楽しかった」
その心の中に刻むために、そう告げた。
ちなみに送られてきた動画を見て破顔する羽目になったのは言うまでもない。
『いつかは、あの日の約束を果たせるように』/リアス
「First grade April」/END
