結婚式の前日。フランスでは、新郎新婦はそれぞれ自分の家族と過ごすのが一般的である。どちらかというと家族大好きなエイリィも、その一般的に倣ってこの前日はクロウ家で過ごすことになるんだが。
「逢いたかったよクリス~!!」
「んぅー…」
血の繋がった家族でないクリスティアも同伴することに俺が大変困惑している。
いいんだ、いいんだクリスティアがいるのは。むしろ大変ありがたいものだと思う。クリスティアは癒しだし、義父も気に入ってはいるのか彼女には優しいし。話も比較的しやすくなる。何しろ眠れてるだろうかだとか何か起きたりしないかの不安もなくなるから大変ありがたい。ありがたいんだが。
「……いいのか本当に……」
思わずそう聞いてしまう。いや今聞いたからと言ってこの就寝前にどうしろとという話だが。
家族水入らず。別に永遠の別れというわけではないが最後の日になるのに。
気に入ってるとは言え、本来であるならば部外者として追い出されてもいいはずの恋人を招いてもよかったのかと。
すべてを口には出さないけれど、聞いた。
けれどベッドの上でうりうりとクリスティアに抱き着いているエイリィは笑顔で頷く。
「もちろんだよっ! リアスだって嬉しいでしょ?」
「まぁ大変ありがたいはありがたいんだが……」
「それに未来の家族を一人のけものになんてできないもん。ねークリス?」
「ねー…?」
眠いせいであいまいな回答になってるぞ。
けれど本人達はまぁ嬉しそうなので。
「……いいなら、いいんだが」
結局諦めて、ベッドヘッドに寄り掛かるしかなかった。とりあえずこの問題は解決したとしてだ。どうしようもできまいし。
「ところでエイリィ」
「はーいなぁに?」
自分達が今いる場所を見て。
「……本当にこのベッドで三人で寝るつもりなのか?」
「本当だよっ!」
いつもより狭く感じる自室のベッドに関して聞いたら笑顔で頷かれてしまった。いや本気だったのかこれ。
クリスティアも入った家族水入らずの食事が終わって、明日も主に俺が早いだろうし眠るかと寝る支度を整えて。眠る前に話そうとエイリィが来たまではよかったんだ。枕を持っていたことには若干疑問はあったが。
そして彼女はそのまま当然のように、世話になっていたとき無理言って買ってもらったダブルベッドに座るだろう。クリスティアとかわいらしく戯れて。
何故かそのまま布団に入るじゃないか。
こいつこのままここで寝る気ではあるまいか? と思って聞いてみたのだが。
「やっぱり未来の妹と大好きな弟に挟まれて寝たいじゃない!」
本人も言っている通り本気でここで寝る気らしい。さりげなく真ん中狙ってやがる。
「……言っておくがあんたが入る時点で俺はこのベッドから降りるからな?」
「えぇっ!? なんで!?」
いやこちらが何故と聞きたい。
「嫁入りを前日に控えた女が男と同じベッドに入るなよ……」
「姉弟ならいいじゃんっ!」
「姉弟と言えど血は繋がってないからな。別にあんたにこれっぽっちも気を起こす気はないが」
「エイリィ、こんなに魅力的なのに…?」
「恐らくお前だけはその発言してはいけないな?」
変な既成事実作らせようとすんな。
眠くて俺に抱き着いてきたクリスティアに溜息を吐きながら。
「……クリスティアと布団に入るのは譲ってやるから。俺は床で寝る」
「体休まらないじゃないっ! 明日は大事な式だよ!」
「そう思うなら自室に帰ってくれないか??」
俺の安眠を願うならばぜひ自室に帰ってほしい。いや寝ないけども。
だんだんとまぶたを閉じていってるクリスティアの頬をくすぐり、身をよじる恋人に笑みをこぼす。そんな俺を見てクリスティアも笑い、ぎゅっと抱き着いて来てまたまぶたを閉じていった。そろそろ本気で寝るなこれは。
「寝そうだが」
「えぇっ、クリス、お姉ちゃんのお胸においで!」
「んぅ…」
手を伸ばすエイリィの声は聞こえているのか、俺に抱き着いたまま恋人はふるふると首を横に振った。
「……残念だったな、振られたぞ」
「うわぁんセフィルーっ!」
「明日慰めてもらえ」
なかなか騒がしい声を聞きながらも睡眠に入ったクリスティアの頭を撫で、布団をかけてやり。
「あんたももう寝ろ。早いだろう」
「もう少しお話しようよーっ、最後の日なのに!」
「だったらもう少し早めに来るんだったな」
九時なんで一般的には早いんだろうが。うちの小さな恋人にはこれを越えると夜更かしである。むくれているエイリィを横目に、一度クリスティアを離してベッドから立ち上がった。
「んぅ…?」
「電気。消して来る」
「クリス! ほらお姉ちゃんこっちだよ!」
「…」
「うわぁんクリスが甘えてくれないっ!」
ぼふっと枕に埋もれてしまったエイリィに思わず笑って、足は部屋の出入り口へ。今日は鍵を閉めるのはやめておいて、扉付近にある電気のスイッチを押して部屋を暗くした。
「そこのライトつけてくれ」
「はぁい……」
すねながらもエイリィがつけた小さな明かりを頼りに、ベッドへと戻っていく。頑張って起きていたのか、ベッドに再び座ればクリスティアが抱き着いてきた。可愛らしい恋人の頭をゆっくりと撫でてやり、睡眠を促してやる。
「かわいいねぇ……」
「ずっと見ていたくなるだろう」
「ほんとに……。カリナから送られてくる写真が最高でね?」
あいつ個人情報流しすぎじゃないか??
「……そろそろカリナを咎めないとな」
「えぇっ!? 私の至福の時間なのにっ!」
「せめて恋人の許可を取ってくれ。それとセフィルにもう少し愛情注いでやれ」
「十分注いでるよーっ!」
これは「どこがだ」というツッコみ待ちだろうか。むくれてしまったのでそうではないと判断して。
「君たちがもう少し写真とか送ってくれればいいんだよ!」
「まぁな……。現像とかしてくれるのがカリナだから直接そっちに送るのもわかるっちゃわかるんだが」
「おかげでブンカサイとかタイイク? のお祭りとかすっごい楽しそうな二人見れてるよ♪ 思わずにやにやしちゃった!」
あの女どういうもの送ったんだろうか。
しかし今から探すとなると朝になるな。精査は後日に回すとして。
「……!」
エイリィがいきなり起き上がったので、思わずそちらに目を向けた。立っていると地面に着くんじゃないかというくらい長い茶色の髪を、耳に掛けながら。
「はー……嬉しいね」
「……」
「クロウ家最後の日に、大好きな弟と未来の妹と喋ってるの」
「……そこは基本的には両親だと思うんだがな」
血の繋がった、とまでは今回言わずに。クリスティアの髪を撫でた。
「私は君たちがよかったんだよ」
「……」
「初めて弟が家に来た時、ほんとに嬉しかったなぁ……」
膝を抱いて思い出し、エイリィは笑う。その笑みを見て、今からもう六年ほど前になる出逢いを思い出した。
無機質な目で俺を引き取りに来たハイゼル。クリスティアを守るように立てば、ハイゼルは旧友だったらしい、今のクリスティアの義父であるアシリアも紹介した。旧友ならば、と多少行き来もしやすいだろうと了承した、クロウ家に入った日。
家に行けば、まだ幼いエイリィが玄関で待っていた。
「……来た瞬間、ものすごい笑顔でこっちに来たもんな」
「弟だっ!! ってね!」
今でもその光景は覚えている。
本当に嬉しそうに、自分は今この世に誕生したんじゃないかと思うくらい、きらきらと輝いた目を向けられた。自己紹介をされれば返す間もないまま手を引かれ。家の中をぐいぐいと引っ張りまわされて。
「行くところがあるからと言えば一緒に行くと言ってな」
「すぐクリスティアに逢ってねぇ。まだ二人が十……十一? くらいだったからいきなり恋人だなんて聞いてびっくりしちゃったけど」
「その次の言葉が”未来の妹だ!” だからな」
思い出して、二人して笑ってしまう。
「天使だから長生きだとはわかったんだろうが。子供の”恋人”発言でそう言われるとは思わなかった」
「そのあとはもうずっとリアスにクリスのこと言ってたよねぇ」
「あぁ」
かわいかっただとか、天使がいたとか。本当に天使だがと返せばそういうんじゃない! と言われ。もっと仲良くなりたい、どうやったら仲良くなれる? 明日も遊べる? なんて。
警戒心を抱く間もなく、ずかずかとテリトリーに入って来た義姉。そうして、その義姉は。
「……あんたの”姉に任せて”にはよく救われてたな」
年頃で姉さんぶりたかったのか。小さなころはそれが口癖で。
俺達二人を、いろんなことから守ってくれた。
「パパに怒られてるとき、クリスと一緒にパパの前に飛び出したよねぇ」
「女に弱いのか娘に弱いのかわからないが、それでその件がなかったことになったな。義父のところに行くときはクリスティアを見ていてくれたし」
「見てるんじゃないよ! 一緒に遊んでるの!」
「あぁ」
精神的に削られて部屋に帰ってきたとき、一緒に本を読んでいた二人が揃って顔を上げて。「おかえり」と笑ってくれたのには何度救われたか。
「……なにかあればすぐ”姉に任せて”、だったな」
身長が届かなくて取れそうにない菓子も。天使なのだから羽を出せるのに、エイリィは”お姉ちゃんに任せて”と意気込んではテーブルやら椅子やらに上がって取ってくれて。
外に行くとき、俺が不安だったならカリナたちと同じようにいろいろと調べてくれて人のいないところによく連れて行ってくれた。クリスティアを何より喜ばせてくれて、理解してくれて、守ってくれて。
「……感謝している」
素直に、言葉が出た。
明日から、クロウではなくなる彼女に。
「……こんな風に話してると、なんか涙出ちゃうねぇ」
「俺はそうでもないが?」
「ふふ、いじわる」
笑う義姉の声はほんの少し涙交じりで。そうでもないと言いながら、喉は少しだけ熱かった。
見なかったふりをするように、視線を小さな恋人へと移す。俺の服に顔をうずめている恋人は、どことなく。肩が震えているように見えた。
それにこっそりとほほ笑んで。
鼻をすする音を聞きながら、明日は笑顔で見送れるよう頑張れと。
小さな恋人の髪を、優しく撫でた。
『結婚式前夜』/リアス
フランスの結婚式では、当日まで新婦の母親以外は新婦のウエディングドレス姿を見ないという。
日本であるならば恐らく共に選ぶことも楽しみなんだろうが、こちらでは当日のお披露目がある種の楽しみであると言える。
つまり親族である俺ももちろん、本日もう一人の主役であるセフィルも、義姉のウエディングドレス姿は今日が初めてなわけで。
「彼女のドレス姿、とても楽しみだね」
お披露目の場となる市庁舎の一室の前。新郎ということで真っ白いタキシードに身を包んだセフィルに、頷いた。
頷いたのはいいんだが。
「……大丈夫か」
ドアノブにかかった手が心なしか震えているように見えて思わず聞いてしまう。レグナに作ってもらった紫のワンピースに身を包んだクリスティアと共に伺うように見上げれば、セフィルはぎこちなく微笑んでいる。
「平気だよ」
「手、ふるえてる…」
「ふふっ、クリスティア、僕はこの震えのことを知っているんだ」
「…? 緊張…」
「違うよ」
セフィルはその若干ぎこちない笑みのまま、けれど得意げに。
「武者震いと言うんだよ」
正確には緊張や恐れを表す場合にも使われると言うのはさすがに空気が読めなさすぎだろうか。
自信満々に「緊張による震えではない」と胸を張っているので今回はそんな野暮なことは避けようかとクリスティアと頷き。
「行こうか」
義理の兄になる男に若干の可愛さを覚えてクリスティアと共に笑いで震えそうになりながら。
セフィルに頷いて、開かれたドアの中へと入っていった。
「いらっしゃい三人とも。新婦の準備はできていましてよ」
入ってすぐに出迎えてくれたのはシェイリスだった。ドアの付近にはハイゼル。三人揃って無意識に会釈をして。
「エイリィー…」
いち早く彼女の方を向いたクリスティアの声に、セフィルと部屋の奥へと目を向ければ。
「……」
「わぁ……」
真っ白いウエディングドレスに身を包んだ、義姉がいた。
ヴェールを被り、椅子に行儀よく座っている姿はどことなく。いつも以上に大人っぽく見える。思わずセフィルと共に魅入っている間に、クリスティアはエイリィへと近づいて行った。
「エイリィきれー」
「クリス?」
「うんっ」
いつも以上に大人っぽい彼女は、その大人っぽい笑みのままクリスティアへと手を伸ばし。
「わぁクリスー!! 今日すっごいかわいいね!? 最高だよ!!」
せっかくの大人っぽさを台無しにするくらいはしゃいでクリスティアを抱きしめた。
待て待て待て。
「ドレスにしわだとかいろいろよくないだろうそれは!」
「大丈夫だよっ、レグナが作ってくれたんでしょうこれ! そんな素敵なものにしわとか一切つけないから!」
「こちらでなくあんたのドレスがまずいだろ!」
「あっでも興奮しすぎて鼻血出しちゃったらごめん!」
「二重の意味で今すぐ離れろ!!」
俺の周りには鼻血を出す奴しかいないのかっ。急いでクリスティアとエイリィのもとへ行き、半ば守るようにクリスティアを後ろから抱きしめてやる。少々エイリィが不服そうだがこればかりは許して欲しい。
「うぅ、クリス~……」
「またあとで…」
「あとでだったら抱きしめさせてくれる!?」
「カリナと順番…」
「わぁ、じゃんけんしなきゃっ!」
先ほどの大人っぽさが嘘のようにはしゃぐエイリィに一度溜息を吐き。思わずセフィルの方を見た。
一瞬、義父の手前ではあるが「義姉がすまない」と言おうとしたが。
「今日もエイリィは最高だね」
類は友を呼ぶというのか。恋人までも呼んでいるらしく。こんな義姉をセフィルはうっとりと見つめていたので何も言うまいと口を閉ざした。
♦
「最高ですわクリスっ!」
「わぁい…」
「ここでもか……」
「クリス相変わらずモテモテだね」
エイリィの熱望により、一足先にウエディングドレス姿を見せてもらったあと。親族とは分かれ、市庁舎の会場の方へと向かえばクリスティアの恰好を見たカリナが淡い桜色のドレスを舞わせながら恋人を強く抱きしめる。それに呆れながら、中へと進み席に着いた。
「エイリィさんのことだからバージンロードも一緒に歩いて! とか言われなかった?」
「もれなく言われたが?」
先に隣に座ったレグナに言えば、予想通りなのか驚くことなく笑う親友。
こちとら断るの本気で大変だったからな。
「最終的にはクリスティアもリアスも手繋いで歩こうと半泣き状態で言われたんだが」
「あの人すげぇ二人のことガチ勢だよね」
「共に過ごしていた四年ほどで何故あそこまでなったのかは心底謎だ……」
「クリスティアガチ勢なのはわかるんですけれどね。気持ちは大変理解できますわ」
「今回ばかりはお前に同意してやる。あそこまで俺に親身になる理由がわからん」
レグナとは反対側の隣に座ってきたクリスティアの奥に座るカリナを見れば、そいつも意味わからんという顔で肩をすくめる。そうだよな、謎だよな。
そうしてクリスティアを見れば。
「♪、♪」
自分はわかると言いたげに、ご機嫌そうに微笑んでいる恋人と目が合った。
「……お前はわかると?」
「もちのろーん…」
「クリスがわかるとなるとレグナもです?」
「まぁ、身内なら気持ちはわかるんじゃない」
相変わらずこの二人で気が合うな。絶対これカリナも思ったよな、「納得いかない」と。
「今お前の心が自分のことのようにわかる自分が憎い」
「わかりますわリアス、ついでに言えば”クリスと一緒ならよかったのに”と思っているでしょう」
「その通りすぎてそろそろお前と同一人物だったんじゃないかと錯覚が起きそうだ」
「奇遇ですわ」
なんて馬鹿なことを言っていれば気が合うクリスティアとレグナは二人そろって体を震わせる。こういうところも気が合うのか……なんてカリナと同じような目をしたとき。
「来るよ」
「!」
声を震わせている親友に言われ、頭を切り替えた。
クリスティアの背を叩いてやれば、先ほどの会話はもういいのか笑っていたことなど嘘のように会場の入り口に目を向けている。それに微笑んでやって。
市庁舎の入口へと、俺も目を向ける。
祝いの曲が流れ始めたのと同時に扉が開いた。
「セフィルー…」
一番に出てきたのは、新郎であるセフィルとその母。腕を組み、ゆっくりとバージンロードを歩いていく。
曲に合わせながら一歩一歩歩いて行っている途中で、今度は義母・シェイリスが。また一定間隔を開けて、今度はセフィルの父が一歩一歩バージンロードを歩いていく。
ときには二人、ときには一人がその道を歩いていくのをぼんやり見ていれば。
「! エイリィ」
視界に、義父のハイゼルと義姉・エイリィが入った。
腕を組んで、隣同士でゆっくりとバージンロードを歩き始める。はしゃぎそうな恋人の腹に腕を回して緩く制してやりながら、世話になっている人々が歩いていくのを見た。
「……」
あの部屋での子供っぽさが嘘のように、どこか大人のように微笑んでいるエイリィ。ゆったりと歩いていく途中で、ときおりハイゼルとほほ笑み合い。そのあとセフィルを見ればいいものを、何故かきょろきょろとしだす。
「探してんじゃない」
「こんなときまで俺達か……」
「愛されてなによりですわ」
「わー」
むずがゆく感じながらも、エイリィが顔を動かしているのを見る。何度か右往左往したあと、ふっと顔を上げた。
「……!」
そうして、血は繋がっていないはずなのに紅い、彼女の目と合う。まさかこんなところで名前を呼んだりはしないかと一瞬はらはらしたのもつかの間。
「……」
エイリィは心底嬉しそうに微笑んで、ようやっと前を向いた。
先ほどとは違って自信を持ったように、胸を張ってセフィルの方へと足を進めていく。
そんな義姉の姿に誇らしさ半分、疑問も少し。
だって思うだろう。そんなに自分達は彼女の中で大きな存在だったんだろうかと。
姉弟になって約七年。共に過ごしたのは四年ほど。
きっと他の奴ならば結構な時間なんだろう。けれど今の俺達にとっては、四年というのはあっという間な、ごく短い時間である。
それでも、ああやって一目見ただけで。自信になるような、そんな存在にはなるんだろうか。
まだきっと、しっかりと理解はできないのだろうけれど。
「……家族というものは不思議だな」
小さくこぼした言葉には、同意をするように。
ほんの少し冷えた手が重ねられた気がした。
♦
「クリスー!」
「エイリィー…」
そうして誓いの言葉やらライスシャワーやら、結婚式の伝統を行ったあと。
結婚式が長いと言われるフランスらしく、結婚パーティーということで市庁舎から場所を移動していき。
「はぁああかわいい……ほんとにかわいいよクリス……!」
「ありがとー…」
ところ変わって式場にて。先ほどの大人っぽさがまた嘘のようにエイリィがクリスティアを抱きしめている。
「エイリィもウエディングドレス姿かわいかった…きれいだったー…」
「クリスに勝るものなんてないよ!」
「照れるー…」
「もっと照れていいんだよ!」
表情に出ないことなど全く気にしていないエイリィは、そう言ってまたクリスティアを強く抱きしめる。先ほどと違う紅いドレスに身をまとったエイリィはクリスティアにとって注目の的なんだろう。もとよりエイリィに対しては拒絶などはないが、いつも以上にべたべたとくっついている。別に構わないんだが。
「……エイリィ、そろそろ時間だろう」
「えぇぇ……意地悪だよリアス、もうちょっと!」
「いや意地悪だとかそういうんじゃなくてだな……あんたが行かないとパーティー自体始まらないだろう……」
「そうだけどーっ!!」
「ダンスが終わったらまたたくさん触れ合えるじゃないですか。ねぇクリス」
「うん…」
名残惜しいというような表情のエイリィを、クリスティアはじっと目を向けて。
「あとでまた、あそぼ?」
こてんと首を傾げながら言えば。
「うぅうっ……かわいい妹に言われたらしかたないよね……!」
「まだ妹じゃないだろ」
「クリス! あとで一緒に踊ってくれる!?」
「リアスが許してくれたら…」
「リアス!!」
聞けよ話をと思うが、切羽詰まった顔で見られたのと、だいぶ長い間周りを待たせていてしかもその待たせているのが身内ということもあり。小言はいつかにして一度溜息を吐いてから。
「……考えておくからさっさと行ってこい……」
「わぁっ、絶対だよ! 約束だよ!!」
「わかったから」
苦手な約束も簡単に取り付けて、エイリィはドレスを翻して式場の中央へと走っていく。それを見送って。
「……嵐のような義姉だな本当に……」
「悪くないって思ってるくせに」
楽しそうに笑う親友を一度肘で突きをかまして、新婦とその父、そして新郎とその母で行われる最初のワルツに、目を向けた。
これが終わったら恐らくまたエイリィが来るんだろう。この時間は少し気が休まって――
「あれが終わったら一緒に踊りましょうねクリス」
くれないなと瞬時に理解した。待とうか。
「カリナ」
「はいな」
「聞き捨てならないんだが」
「あら、何かおかしいことを言ったでしょうか」
「明らかに順番で言ったら俺とクリスティアが踊るだろう。踊るとすればだが。なにちゃっかり自分が行こうとしてるんだ」
「順番的に私じゃないですか」
「おかしくないか??」
「親友同士で踊ってそのあと恋人や親族でしょう?」
ちょっと待て。
「その理屈で言ったら俺とリアスで最初おどんの?」
「そうなるよな??」
こんなときにまで腐女子発揮してんじゃねぇよ。
「こういうときぐらいおとなしくできないのか……」
「私別にあなた方に踊れなんて一言も言ってないんですけれどね。言葉足らずは認めますが。とんだ風評被害ですわ」
「こっちのセリフだろ」
「というか、最初にそういう発想ができるようになったということは少なからずなじんできたってことですかね、龍蓮」
「違うわ」
おいクリスティア、「まじですか」みたいに顔を輝かせるな。
「お前はもう少し俺の方を頑張ってほしい。マジで」
「龍蓮もすてきだと思うの……」
「まずは正規ルートクリアしてからにしてくんない? こっちイフルートだから」
「カリナ、イフルート確定した」
「雪巴さんたちに相談して攻略法探っておかないとですね」
結局こうなるのか。
「……ややこしいことしやがって」
「リアスも内心楽しんでるじゃん」
「お前のその言い方だと俺とお前のルートを心から楽しんでいるように聞こえるからやめてほしい」
俺が楽しんでいるのはノリだノリ。
「まぁでも、なんかあったらこっちもいろいろ手打てるし大丈夫だよ。リアス誰と誰がいい?」
なんて、張り付けたような笑みで言う元凶の双子の兄に。
「……とりあえず正規ルートにもっと力を貸してほしい」
優雅に踊る親族を見ながらこぼせば、「それもそうか」と楽しそうに笑われた。
フランスの結婚式の中で最も長いこのパーティーが始まってから早数時間。夜も更け、窓から外を見れば月もきれいに見えるようになった頃。
「…」
「……そろそろ限界か」
小さな恋人がそろそろ限界を迎えそうで、若干船を漕ぎ始めている。
けれどしゃがんで視線を合わせてやれば、クリスティアはふるふると首を横に振った。
「お前今にも倒れそうだぞ」
「んぅ…」
すでにいつもの眠そうな声になっているし。
さすがに倒れるのは困るのでクリスティアに手を伸ばした。
「ねむくない…」
「知ってる」
なんて適当に相槌を打ってやりながら抱き上げてやる。眠くないと言いながらも眠そうにすり寄ってくる恋人が心底愛おしい。
思わず微笑みながら、周りを見渡した。
「ちょっと席外しているみたいですわ」
「あとで声かけとこっか?」
「いや……」
俺と同じく、先にエイリィやセフィルを探していてくれていた双子には首を横に振りつつ、自分でも確認のため会場内を見渡す。揃っていないのか。義母もいないな。
「完全に落ちたらそうする」
「おっけ」
「ねない…」
「あぁ」
緩く体を離してむっとしている恋人に顔を緩ませながら頷いて。再びこちらにすり寄ってきた恋人を強く抱きしめる。
だいたい「寝ない」と言ってもこうしていたら五分は持たないんだがな。ぬくいだとかで。せっかくのイベントなのでできれば起こしておいてもやりたいが、さすがにあそこまでぐらついていたら倒れるのも時間の問題だろう。俺の精神が危ない。
「クリスー、何か冷たいものでも飲みますかー」
「んぅ…」
手では彼女の眠りを促すように背を叩きながら、頭では恋人をどうやって起こそうかと考える。さりげなくレグナが周りのお偉い男たちにけん制しているのを横目に入れつつ、カリナが言った冷たい飲み物を一回頬に当ててやればいいかなんて、若干のいたずら心が芽生えていたときだった。
会場内に、わぁっと歓声が上がる。
「なんだ?」
「あっち側。なんかやるんじゃない?」
「もしかして何かの準備でいなかったんですかね」
そちらの方向を見るが、正直人が集まっていて詳しくは見えない。けれど上がっている歓声的にはレグナとカリナが言ったような何かしらのイベントでもやるんだろう。人混みがある以上俺には無縁だなと、再びクリスティアを起こすための施策を考えるため思考に落ちようとすれば。
「リアス、クリス!」
まさかの名前を呼ばれてしまった。強制参加型かと苦笑いをこぼしつつ、そちらに目を向ける
――と。
「……!」
思わぬ出来事に、自分でもわかるくらい驚いた顔をしていると思った。その顔のまま、腕の中で夢見心地になり始めている恋人の背を叩く。いつもの眠りを促すものではなく。
「クリス」
しっかりと起こすために。
「ん…?」
「クリスティア、起きろ」
「寝てない…」
「あれ」
「れ…?」
少し強めに揺さぶって、顔を上げたのを視界の端に捉えてからその方向を指さす。俺の言われるがままにそちらを向いたクリスティア。
その、小さな彼女の目の先にもいるであろう、視線の先には。
昼間と同様、ウエディングドレスとタキシードに身を包んだ新婦と新郎がいた。
ベールもブーケも、髪飾りも、すべてが昼のまま。その二人はまたバージンロードを歩くように、ゆっくりとこちらへ歩いてくる。
ゆっくりゆっくり、一歩ずつ。
どこか遠くに思えたような大人っぽい笑みを携えながら歩いてくる二人に。本能的に背筋を伸ばして、クリスティアもしっかり立たせるようにと彼女を隣に下ろした。
そうしてゆっくりと歩いてきた二人は、俺達四人の前に立つ。
「えへへ……また着ちゃった」
「何故……」
「エイリィが、どうしてもやりたいことがあってね」
「やりたいこと…?」
「うん! 定番のこと! 向こうではやんなかったでしょ?」
なんて言われるが、四人揃ってピンと来るものはなく。視線を合わせて、全員で首を傾げた。
「あれ、僕らは日本だと定番だと聞いたんだけど」
「あっでもセフィル! 高校生だからまだ参加とかしないかも!!」
「あぁそうか」
いや二人で納得されても困るんだが。いまいち話の状況がつかめない。
「じゃあ僕らが初めてだったかな?」
「えぇと……? お話が少々つかめないのですが……」
「なんか結婚式での儀式、みたいなこと?」
カリナとレグナの問いに、セフィルもエイリィも楽し気に笑うだけ。ますますよくわからず首を傾げてしまう俺達に。
エイリィが、一歩前に出た。
「クリスティア」
「はぁい…」
名前を呼ばれて一歩前に出たクリスティアの前に、エイリィは視線を合わせるようにしゃがむ。
「今回は、大好きなきみにね」
「?」
「きみが大好きなカリナには、きみからやってあげて」
そう言って。
エイリィは、手に持っていたブーケを、クリスティアに差し出した。
「ブーケ…」
「ブーケトスって言ってね。本当はポーンって投げて取った人が次結婚できるってやつなんだけど」
「!」
「私はきみに、渡したかったんだ」
大好きなきみに。
そっと受け取ったクリスティアを、エイリィは強く抱きしめた。
「来てくれてありがとう」
「…」
「クリス、リアス」
次は、
「次はきみたちのが、見たいなぁ」
”いつか”でいいから。
「きっとクリスはすごいかわいいんだろうね」
「…」
「リアスはものすっごくかっこいいと思うの」
「……」
「大好きなきみたちの、素敵な晴れ姿。想像しただけで心が幸せだよ」
――ねぇ。
優しい声で言いながら、体を離して。
紅い目は俺達を見る。
「いつか、結婚式するときは。絶対呼んでね!」
そうして、きっと叶えられることなどない約束を、彼女は願った。
こういうとき、どうすればいいのだろう。
あの頃したいと思った結婚式。けれど叶うことのなかった、小さな幸せ。
そしてそれは、今もなお。ずっと叶えられることはない。
気持ち的に遠ざけていたからというのももちろん理由のひとつだった。けれど絶対的な理由がひとつ。
俺達は、大人になることができない。
時代が流れて、法律が定まって。結婚できるという年齢は男女ともに二十歳から。
俺達は、その年齢になることは延々となくて。つまりは。
結婚をすること自体が、俺達にはもう、できないことである。
けれど義姉はそれを知らない。知る由もない。
レグナもカリナも、その悲しい現実を知っているから何も言わずにいる。クリスティアも、珍しく黙ったままだった。
こんな状況に立たされた時、どう言葉を返せばいいんだろうか。
そう自問しつつも、答えは心の中に浮かんでいた。
一歩前に出て、クリスティアの隣にしゃがみ。エイリィと視線の高さが合う。
「……」
「ね?」
無邪気に笑う彼女に、微笑んで。
俺は、小さく頷いた。
「……あなたの”次”になるかはわからない」
「うん」
けれど。
たったの四年。あっという間なはずの、短い時間。それでも、今まで過ごしてきた他の人間とは比べ物にならないくらい、大事と言える君へ。
そうして、今。
見守ってくれている大事な親友たちへ。
「……いつかは、あなたの前でも、その姿を見せられるよう、努力する」
苦手な約束を、今、再び誓おう。
たとえどのくらい時間がかかったとしても。
きっと手は震えていたんだろう。クリスティアの肩に乗せていた手に、冷たい手が重なった。心の中で「武者震いだ」と言い聞かせて、エイリィを見て。
「……うんっ!! 楽しみにしてるね!!」
「……」
ちらりと、あの頃見せてやれなかった大切な”親友”を見れば。
「……」
今までにないくらい嬉しそうに笑っているから。
たとえ無理であったとしても、心は。
決して諦めることはしないと、あの頃のように心に誓って。
珍しく、「考えておく」だとかあいまいな言葉を口にせず。
「……あぁ」
素直にエイリィの言葉に、頷いた。
『君との約束を、いつの日にか、今度こそ。』/リアス
未来へ続く物語の記憶 July-V
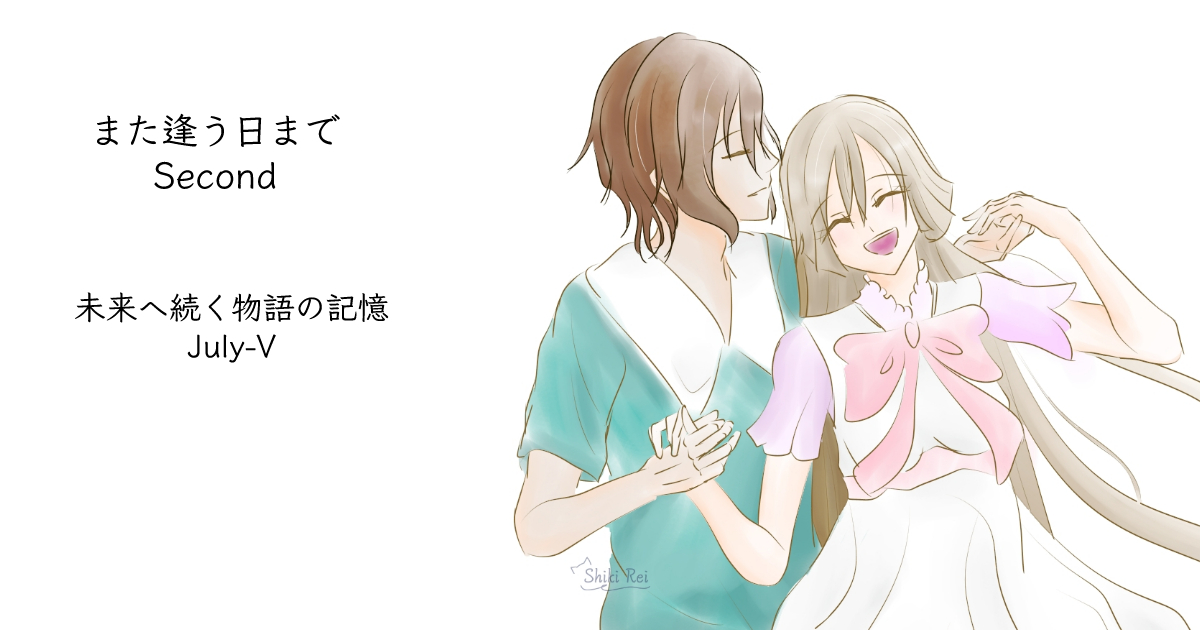 クリスティアに物語を聞かせてもらう
クリスティアに物語を聞かせてもらう